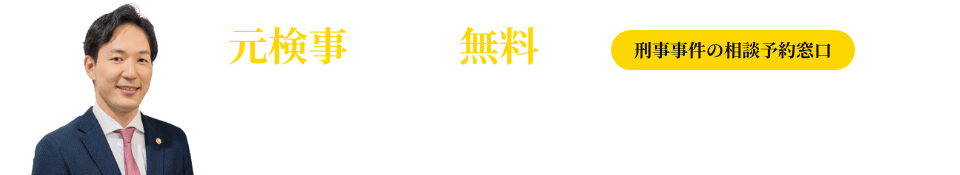不同意性交等罪は、逮捕される可能性も高く、有罪になれば執行猶予にならず実刑(刑務所行き)になる可能性も高い、重い罪です。
この記事では、不同意性交等罪を犯してしまったらどうなるのかと、逮捕・起訴・実刑を防ぐためにどうすべきかを説明します。
1 不同意性交等罪とは
(1)同意のない性交等に対する犯罪
不同意性交等罪は、同意していない相手に性交(セックス)等をすることです。
事件当時に相手が性交等に同意していたり、相手が同意していると思っていた場合は、故意がないため、不同意性交等罪にはなりません。
法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
有罪になると、初犯であっても刑務所行きになる可能性が高いです。
不同意性交等罪を犯して人を死亡させたり怪我させた場合、不同意性交等致死傷罪となり、法定刑は無期又は6年以上20年以下の懲役です。
不同意性交等罪にはさまざまな類型がありますが、典型的には、暴力や脅迫で抵抗できなくした上の事件や、お酒を飲ませて意識を失わせて性交や性交類似行為をした事案です。

(2)年齢によっては同意があっても不同意性交になる
同意がある性交等であっても相手が13歳未満である場合、不同意性交等罪になります。
なお、性交の相手が16歳未満である場合、16歳未満の人との年齢差が問題になります。
相手が生まれた日より5年以上前の日に生まれた人には、同意があっても不同意性交等罪になりますが、相手が生まれた日より5年以上前の日に生まれていない人は罪になりません。
例えば、15歳の人と性交をした人が17歳であれば、同意があれば不同意性交等罪になりませんが、21歳であれば、同意があっても不同意性交等罪になります。
不同意性交等罪・不同意性交等致傷罪とは何かについて、詳しくはこちらをご参照ください。
※これまで、同意していない相手に性交する行為は、強姦罪や強制性交等罪という名前の刑罰で規制されていました。
性犯罪の取り締まりを強化する法改正が続き、2017年に強姦剤が強制性交等罪に、2023年に強制性交等罪が不同意性交等罪に変わりました。
不同意性交等罪、強制性交等罪、強姦罪の違いについては「参考 強姦罪、強制性交等罪、不同意性交等罪の違い」をご参照ください。
法律の詳細は本記事末尾の「参考 刑法抜粋」に記載してあります。
2 不同意性交等罪を犯したらどうなるのか
もし不同意性交等罪を犯し、その後何も対処しなければ、逮捕され、長期間身柄拘束されている間に起訴されます。
適切な対処をしなければ、起訴後も保釈されずに身柄拘束され続ける可能性もあります。
起訴後は、公開の法廷で裁判がなされ、有罪になります。
不同意性交等罪で有罪になれば執行猶予にならず、実刑(刑務所行き)になる可能性が高いです。
有罪になった場合には、刑事損害賠償命令制度という制度を用いて、裁判所に損害賠償を命じられる可能性があります。
この場合の賠償額は、事案にもよりますが、100万円単位になります。
このように、不同意性交等罪を犯した場合、とても厳しい未来が待っています。
不同意性交等罪を実際に犯した場合、簡単ではありませんが、逮捕・起訴・実刑を避けるための対応を取る必要があります。
不同意性交等罪を犯していないのに捜査の対象となっている場合は、他人がした不同意性交について嫌疑をかけられている(冤罪)か、自称被害者がわざと嘘を言っている(虚偽告訴)場合です。
このような場合、事実無根の被害申告で罰を受けることのないように冤罪を晴らすとともに、場合によっては自称被害者に対して虚偽告訴罪で刑事告訴したり損害賠償請求することを検討します。
「性交等はしたけれども不同意性交等をしたつもりはない場合」どうすれば良いかについて詳しくは、こちらをご覧ください。
「性交等はしたけれども不同意性交等をしたつもりはない場合」に示談すべきかどうかについて詳しくは、こちらをご覧ください。
3 逮捕・起訴を避けるために
実際に不同意性交等罪を犯した場合、何も対処しなければ、逮捕され、起訴されます。
逮捕や起訴を避けるためには示談する他にありません。
16歳未満の人と同意の上で行為をした場合を除き、不同意性交等の被害者もその家族も、とても深く傷ついています。
そのため、示談するのは容易ではありません。
しかし、同時に、被害者やその家族にとっては、刑事事件を続けて何度も事件のことを思い出すことも負担になります。
被害者にとっても、刑事事件を早く終えることが望ましく、誠実な対応を尽くすことで示談に応じることもあります。
示談するためには、可能な限り早い段階から行動を起こす必要があります。
もし被害者の連絡先がわかるのであれば、示談することで警察沙汰をも回避できる可能性があります。
この場合、示談金の金額は高く、100万円以上になることも少なくありません。

4 実刑を避ける(執行猶予にする)ために
実際に不同意性交等罪をした場合、逮捕を避けたり起訴を避けたりする活動と同時並行して、もし起訴されたときに実刑(刑務所行き)を避けるための活動をしておくことが大切です。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役であり、重い罪です。
執行猶予は3年以下の懲役に付けることができる制度なので、不同意性交等罪の法定刑では執行猶予をつけてもらうことができません。
この意味で、不同意性交等罪は原則として実刑になる罪です。
ですが、裁判所は、減軽により、法定刑よりも軽い刑罰を下すことができます。
不同意性交等罪も、減軽してもらえれば、執行猶予にすることができます。
法律上、さまざまな減軽がありますが、不同意性交等罪を犯した場合に視野に入れるべき減軽は、以下の2つです。
・自首減軽
・酌量減軽
自首は、犯行自体もしくは犯人が誰なのかが知られる前に捜査機関に自己の犯罪を申告することで成立します。
裁判所は自首を被告人に有利な情状として考慮しますので、執行猶予になる確率が高まります。
犯行自体もしくは犯人が誰なのかが知られる前に捜査機関に申告する必要があるため、被害者が被害申告するよりも前に警察に行かなければ、確実に自首することはできません。
また、酌量減軽は、「犯罪に情状に酌量すべきものがあるとき」になされます。
酌量すべき事情は個別の事案に応じて多様ですが、全ての事案で示談交渉と再犯防止を行う必要があります。
示談して被害者に被害弁償をすることや許してもらうことは有利な情状になります。
また、強制性交等罪を含む性犯罪は再犯率が高いため、裁判官に安心して執行猶予にしてもらうため、再犯予防のための仕組みを構築する必要があります。
5 再犯予防についての重要な考え方
再犯予防において、「もう絶対に同じことをしない」という本人の意思は不可欠ですし、最も大切なものです。
ですが、それだけでは不十分です。
不同意性交等罪は、再犯の可能性が高い重大犯罪です。
不同意性交等罪を行なってしまった方の中には、依存症であったり、強い認知の歪み(考え方や物事の見方が歪んでいて、適切に認識できないこと)があったりする方が少なくありません。
事件直後や逮捕直後は、事件を起こした本人も「もう絶対にしない」と思っていることがほとんどですが、その気持ちは時間と共に徐々に薄れていってしまいます。
依存症や認知の歪みに基づいた犯行の場合、再犯予防は、本人の意思や言葉だけでは足りず、犯行に及んだ原因とそれに対する対処を、医師などの専門家とともに構築する必要があります。
依存症や認知の歪みに対する治療をすることが大切ですし、継続的に治療に通うことも簡単ではありませんので、家族や仲間が寄り添うことも大切です。
寄り添ってくれる人がいなければ、仲間を作るところから始める必要があります。
裁判所も再犯予防体制の構築が重要であることはわかっているため、再犯予防体制の有無は、執行猶予を得る上で必須と言えます。
上原総合法律事務所では、専門の医師にご相談しながら実際に再犯を防ぐための活動も支援します。
6 自首についての重要な考え方
実際に強制性交等罪を犯してこの記事を読んでいる方は、警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも、後悔して苦しんでいる方がほとんどのはずです。
☑ 逮捕されたらと考えると不安でしかたない
☑ 夜も眠れない、すぐに起きてしまう
☑ なんであんなことをしてしまったのか後悔している
被害申告されているのだろうか、いつ逮捕されるのだろうか、自分はどうなってしまうのだろうか、などといった、考えても決してわからないこと考えるのをやめられず、とても苦しい、というご相談は少なくありません。
このような方は、自首をすることを強くお勧めします。
その苦しみは、逮捕されるまで続きかねず、精神を壊す危険があります。
自首した方の多くが、全て話してスッキリした、事件を起こした後悔は消えないけれども、警察にばれているのかなどの疑念から解放されて楽だ、などと言います。
自首した後は、被害者に対する誠実な対応と再犯予防に集中することができます。
自首しないまま被害申告がなされれば、いずれ、ほぼ確実に逮捕され、実刑になる可能性が高いです。
事件に向き合わずに逃げ切ることは困難です。
ですが、自首をすれば、逮捕されたとしても裁判官が勾留しないでくれる可能性が出てきます。
自首すれば、執行猶予がつく可能性も高まります。
被害者にも、反省していることをわかりやすく示すことができます。
そのため、あらかじめ弁護士に相談し、自首後に警察にどのようなことを話すのかを打ち合わせの上、弁護士を同行させて自首するべきです。
7 お気軽にご相談ください
上原総合法律事務所は、元検事の弁護士8名を中心とする刑事事件の専門家集団で、事件を早期解決するための独自のノウハウを有しています。
不同意性交等罪の容疑をかけられた方、性交等をした相手から同意がなかったと訴えられている方からのご相談をお受けいたします。
何もせずに実刑になってしまえば、長期間社会と隔離され、さまざまなことが困難になります。
上原総合法律事務所は、事件に立ち向かい、より良い未来に向かおうとする依頼者に寄り添います。
不起訴を勝ち取ることで、これまでと変わらない人生を送ることができます。
起訴された事件でも、執行猶予にすることで、社会復帰を容易にできます。
早期に弁護士に依頼することで、不起訴や執行猶予の可能性を高めてください。
不同意性交等罪事件を起こした方、疑われている方は、お気軽に、お早めにご相談ください。

参考 強姦罪、強制性交等罪、不同意性交等罪の違い
【被害者・処罰される行為】
強姦罪では、暴行や脅迫などの影響で犯行できない状態の女性に対する性交を取り締まっていましたが、強制性交等罪では被害者の性別を問わなくなるとともに、性交だけでなく性交類似行為も強制性交等罪により処罰されることとなりました。
さらに、不同意性交等罪では強制性交等罪よりも取り締まり範囲が広くなり、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態」の被害者に対して「性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」が取締られています。
【婚姻関係がある場合】
現行法では、婚姻関係があっても不同意性交等罪が成立すると明確化されています。
【親告罪ではない】
かつて、強姦罪においては被害者が女性に限定されていましたし、被害者などの告訴がなければ起訴できない(このような罪を「親告罪」と言います。)とされていました。
ですが、強制性交等罪への法改正により、性交に限らず性交類似行為も強制性交等罪として重く処罰することとするとともに、被害者の性別も問われず、告訴も必要なくなりました。
不同意性交等罪においても告訴は不要とされています。
参考 刑法抜粋
(不同意わいせつ)
第百七十六条次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
第百七十八条削除
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
第百八十条第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら
※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。