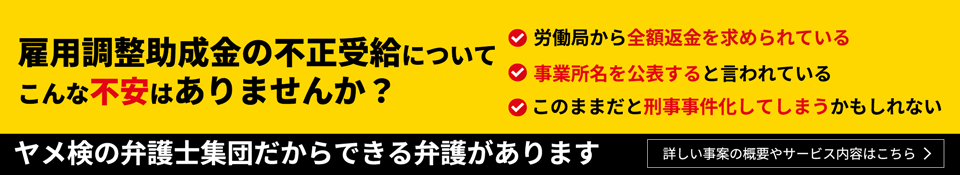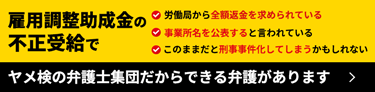雇用調整助成金とは 不正受給でお困りの専門家(税理士・社労士)の方はこちらをご覧ください。 雇用調整助成金に関するセ…[続きを読む]

弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
目次
雇用調整助成金の不正受給に対する調査が厳格化
雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、コロナ禍で受給要件と審査が緩和され、結果として不正受給や不適正受給(過誤受給)が多発しました。
コロナ禍初期の段階では、労働局は、迅速に助成金を支給するというニーズのもとの支給審査に忙殺されており、支給済みの案件の調査については
- 明らかに不自然な申請に対する調査
- 従業員からの内部通報に基づく調査
といった、強く不正が疑われる事案にほぼ限定されていたように思われます。
2022年頃以降は、コロナ禍もやや落ち着きはじめ、助成金の申請とこれに伴う審査にも収拾がついてきたため、過去の申請が適切であったかについて、広範かつ厳格な調査が行われています。
そして現在、調査に基づいて多数の不正受給案件が発覚し、労働局のホームページで不正受給を行った事業者や関与した社会保険労務士等の情報が公表されたり、雇用調整助成金の不正受給で逮捕された人のニュースが報道されています。
また、会計検査院は、厚生労働大臣に雇用調整助成金等の不正受給等に係る事後確認について指摘しています。
会計検査院による主要な指摘は以下のとおりであり、要するに「雇用調整助成金等の不正受給等に対する調査が不十分であり、より徹底した調査を行うべき」という内容です。
- 雇用調整助成金等と休業支援金等との重複支給に関する事後確認が適切に行われていないこと
- 休業支援金等の二重支給に関する事後確認が行われていないこと
- 雇用調整助成金等に係る実地調査の対象事業主の範囲が適切に設定されていないこと
会計検査院の指摘を踏まえ、厚生労働大臣は記者会見において「制度の信頼を揺るがす不正受給を見逃すことのないように、調査の充実とその結果に基づく厳正な対応に努めてまいりたい」 と述べました。
これらの事情も踏まえ、 厚生労働大臣の指示を受けた厚生労働省や労働局が、不正受給の有無の調査をさらに増やして厳格な対処をしたものとうかがわれているところですし、この状況は今後もなお継続すると見込まれます。
また、労働局主導の調査のみならず、会計検査院主導の調査も引き続き行われる可能性もあります。
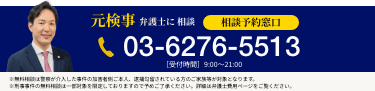
雇用調整助成金等の不正受給の調査はいつまで?
以上のとおり、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等の不正受給の調査は引き続き厳格かつ広範に実施されることが見込まれます。
では、助成金の受給後、どのくらい経過すれば安心できるのでしょうか。
この点については、少なくとも助成金の支給から5年間は調査の対象となる可能性が否定できないと思われます。また、それ以上の時間が経過しても、完全に安心してよいとまでは断言しにくいのが実情です。
5年という期間を踏まえると、コロナ禍の初期、2020年(令和2年)頃に受給した助成金については、そろそろ調査の対象となる可能性は低くなってきているかもしれません。
しかし、ここで注意が必要なのは、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、基本的に1か月をひとつの判定基礎期間として、各月分を繰り返し申請・受給しているという点です。
コロナ禍が長引いた結果、2,3年にわたり雇用調整助成金等を受給したという会社も少なくないでしょう。
そのような場合、申請初期のものについては既に5年が経過しつつあるといっても、まだまだそのような状態に至らない受給が多く残っているため、調査対象となる可能性は十分にあると言わざるを得ません。
訪問調査・立入検査等の対象とされる確率・可能性は?
これまで労働局等から何のコンタクト等もないという場合、もう自分たちは調査の対象にはならないのではないかと思われるかもしれません。
しかし、結論から言えば、これまで何の連絡等もなかったからといって安心できるわけではありません。
既に述べた通り、当初は労働局側の人員等の問題でそもそも調査が困難な状況でしたし、調査を始めるにしても、強く不正が疑われる事案や受給総額が極めて大きい事案などが優先されていたと思われます。
より広範囲かつ厳格な調査がされるようになってからも数年は経過してはいるところですが、優先されていた事案の調査が終結をむかえ、調査のために補充されたと思われる人員の手が空きはじめたであろう結果、むしろこれまでは後回しにされていた事案についても調査対象とされるようになっているのではないかという印象すらあるところです。
また、しばしば「全件を調査対象としている」などといった話も見聞きするところであり、訪問調査・立入検査等の対象となってしまう確率は決して低いとはいえませんし、リスク管理の観点からは、これまで何らの調査等がなくとも、いつかは調査の対象となると考えておくべきでしょう。
例えば、厚生労働省は休業支援金等の支給データも持っているため、今後、雇用調整助成金を受給しているのに従業員が休業支援金を受給してしまっている(重複支給、と呼ばれています。)などの会社への調査が見込まれます。
また、会計検査院は「重複支給のあった会社や従業員について他にも不正受給をしていないかを調査するべき」としています。
実際に、不正受給をしてしまった会社の代表や役員が他の法人でも受給している、不正受給に関与した社労士が他の申請・受給にも関与しているといった事情があれば、関係する会社等も調査の対象となっている場合は頻繁に見受けられます。
さらに、労働局側に余力が生じ始めたからかもしれませんが、特段の理由も見当たらないのに突然労働局から連絡が来たという話も少なくありません。
なお、訪問調査・立入検査の確率という意味では、調査対象となったからといって必ず会社やお店への訪問・立入を伴うとは限りません。
ただ、多くの場合において労働局側は会社等への訪問・立入を行おうとしてくるところ、早期に自主的な調査をして問題点を報告するなどしてもはや訪問・立入の必要がないと判断されたり、あるいは会社事務所や店舗が既に引き払われていて訪問のしようがないなどといった例外的な場合には実施されないという印象です。
雇用調整助成金の調査内容は?
労働局等は
- 申請が真実に合致するものだったのか
- 真実に合致しない場合、なぜ行われたのか
- 真実に合致しない申請であることを認識していたか(故意の不正受給なのか)
などを明らかにしようとします。
この調査は、確定申告書・決算書・総勘定元帳・損益計算書・売上証票・雇用契約書・労働者名簿・休業協定書・タイムカード・シフト表・給与明細・賃金台帳等の客観的な資料に基づいて行われることもありますし、経営者や従業員、取引先等からの聞き取りによって行われることもあります。
具体的な進行としては、まず
- 労働局から書面が届き、期限までに上記のような資料の提出を求められるパターン
- 労働局から連絡があり、訪問調査・立入検査を行うと告げられるパターン
- いきなり労働局が事業所に訪問してきて立入検査が行われるパターン
などがありえます。
このうち最も多いのは資料要求から始まるパターンかと思われ、中には特段の疑いがなくともこの形で調査対象となることもあるという印象です。
他方でいきなりの訪問は必ずしも多くなく、実際には労働局が事前に調査を進めていた中、連絡がつかなかったりなどの事情でやむなく訪問するというケースもあるようです。
なお、いずれの場合でも、労働局から直接のコンタクトがあった時点では、既に従業員や取引先への調査が進められているという可能性は十分にありえます。
また、労働局から連絡を受けた従業員等が会社に相談することで調査が行われていることを知るといったパターンもあります。
労働局からの資料要求、立入検査、ヒアリング等は一度で終わるとは限らず、むしろ疑いがあれば何度も繰り返されます。
最終的には担当する労働局での面談等も行い、代表者等の「聴取書」を作成するという流れが一般的です。
調査には時間もかかり、事案によっては数年に及ぶこともあります。
一度疑念を抱かれるとその疑いを晴らすのは簡単ではありませんし、一部不正ないし不適正があってそれを認めても、他にも問題があるのではないか、不適正(過誤・ミス)ではなく故意の不正受給ではないかなど、調査する側は疑いの目で見てきます。
それらに対し、適切な資料の提出や説明をしていくことは専門家でもない限り容易ではありませんし、本来の業務を行いながら調査に対応していくことはかなり負担です。
なにより、多くの事業主の方が精神的にも強い負担を感じられているのが実情であり、場合によってはそのことで事業にも影響が生じかねません。
不正受給が発覚するとどうなる?
労働局等の調査の結果、不正受給に該当すると判断された場合、どうなるのでしょうか。
この点については、雇用保険法施行規則や「雇用関係助成金支給要領」に定めがあります。
この要領では、労働局による措置として、
- 支給決定取消
- 返還命令
- 不支給措置
- 公表
などが定められています。
また、刑事訴訟法第239条第2項は、
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
と定めており、労働局が捜査機関に対して刑事告発を行うこともあります。
不支給決定取消・不支給決定について
不正受給が発覚した場合、既に支給を受けた助成金については支給決定の取消決定が行われ、申請はしたもののまだ支給されていなかったものについては不支給決定がなされ、それぞれ申請者に通知書が送付されます。
これにより、既に支給を受けた助成金については次に述べるとおり、返還する義務が生じます。
返還命令について
労働局により不正受給と認定された場合には、既に支給を受けた助成金の返還を求められることになります。
また、その場合、受給した額を返還すれば済むのではなく、返還を求められた金額の20%に相当する金額の納付も求められることになります。
さらには、不正受給の日の翌日から返還の日まで、原則として年3%の割合で算定した延滞金の納付も求められます。
このように不正受給と判断された場合には、制裁として、支給を受けた助成金の金額よりも多額の金額を納付しなければならなくなることに注意が必要です。
これに対しで、不正受給ではなく、故意なく過大な支給を受けてしまったといった不適正受給(過誤受給)との判断である場合には、正しく申請等すれば受給できるはずであった額を超える部分のみの返還となるのが通常です。
不支給措置について
不正受給を行った事業主等は、支給決定取消等から5年間、雇用関係助成金の支給を受けることはできません。
また、不正受給を行った事業主等の役員等であって不正受給に関与した者が、他の事業主等の役員等となっている場合には、当該他の事業主等についても、同様に5年間、雇用関係助成金の支給を受けることができません。
これにより、不正受給と判断されてしまった場合には、将来にわたって、ハローワークで取り扱うほぼすべての助成金の支給が受けられなくなってしまいますし、場合によっては自分の会社だけでなく、役員となっている他の会社にまで影響が及ぶ可能性もあるのです。
公表について
雇用関係助成金要領によれば、不正受給が「特に重大又は悪質なものであると認められる場合」等には、原則として、事業主等の名称を公表するものとされています。
公表の際には
- 不正受給を行った事業主等の名称、代表者及び役員等(不正受給に関与した役員等に限る。)
- 不正受給に係る事業所の名称、所在地及び事業概要
- 不正受給に係る助成金の名称、返還を命じた金額及び返還状況
- 事業主等が行った不正の内容
- 社会保険労務士が不正受給に関与していた場合は、事務所の名称、所在地、氏名及び不正の内容等
が公表されることになります。
公表の方法は、記者発表に加え、管轄労働局のホームページに掲載することにより行うとされており、ホームページへの掲載は、原則として、支給決定取消等から5年が経過するまでの期間行うこととされています。
このように不正受給を行ったことを長きにわたって公表されてしまうことは、企業の社会的評価(レピュテーション)を大きく低下させるものであり、取引先や従業員からの信頼低下を招きかねないものです。
そのため、不正受給が疑われる場合には、速やかに事実関係の調査を行い、公表を防止するための方策を講じていくことが肝要です。
具体的には、不正受給に該当すると判断できる場合には、「特に重大又は悪質なもの」と評価されることを防止するため、不正受給に至った原因や再発防止策を含めて調査結果を速やかに労働局に報告するとともに、労働局から返還を命じられた金額を一括して納付することなどが重要と考えられます。
また、現状労働局側は、不正受給に該当する場合であっても、その額が100万円未満の場合や、調査前に「自主申告」があり、かつ返還命令後1か月以内に全額を納付した場合には公表しないこともできるとの基準も明らかにしており、これらの条件を満たすことが可能であれば、自主申告等による公表回避という選択もありえます。
そのためには、まずは専門家に依頼して自主的な調査等を行い、不正受給に該当するのかなどを確認した上で対応を検討することが重要です。
刑事告発について
前述のとおり、刑事訴訟法第239条第2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めています。
この条文によれば、労働局の職員は、不正受給が詐欺等の犯罪に該当すると判断した場合には、必ず捜査機関に対して刑事告発をしなければならないようにも読めます。
しかし、刑事訴訟法上はそのようには解釈されておらず、告発を行うべきか否かは、事案の重大性であったり、今後の行政運営に与える影響等を総合的に考慮し、慎重に検討して判断されることも許容されていると解釈されています。
そのため、重大な事案と評価されたり、今後の助成金の運営に悪影響を与える事案であると評価されたりするのを防止するためにも、不正受給が疑われる場合には、速やかに事実関係を調査した上、不正受給に至った原因や再発防止策を含めて調査結果を速やかに労働局に報告するとともに、労働局から返還を命じられた金額を一括して納付することなどが重要と考えられます。
労働局・会計検査院による現地調査・立入検査がきたらどうすればいい?対応方法は?
労働局や会計検査院の調査は、いきなり担当者から電話で連絡が来ることもありますし、「資料提出のお願い」などといった手紙が届くこともあります。また、会社やお店への連絡より先に、従業員や取引先に対する聞き取り等が行われる場合もあります。
まず、基本的な姿勢として、上原総合法律事務所では、労働局や会計検査院の調査に対しては協力するなど、誠実に対応すべきであると考えています。
なぜ労働局や会計検査院の調査に誠実に対応した方が良いのでしょうか。
労働局は、雇用保険法に基づいて、雇用保険被保険者を雇用している事業主に対して、報告を求めたり、文書の提出を求めることができます。
報告・提出命令に違反した場合は、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
となる可能性があり、
会社としては、調査に協力すべき義務があります。
ただ、この義務を度外視しても、調査に協力することが会社にとって有益だと考えます。
もしも不正受給をしていた場合には、例え会社がこれを隠ぺいしようとしても、従業員や取引先等からのヒアリングなど含め、様々な調査方法があるので、いずれ不正受給であったことが発覚すると考えられますし、そうなった場合、事後的な対応を含め悪質な事案と判断され、公表はもちろん、刑事告発の対象となってしまうリスクが高くなります。
また、そもそも労働局からのコンタクトがあった段階で、既に労働局等に不正受給であることが発覚し、労働局側が重要な証拠等も入手している状況かもしれません。
不正受給をしてしまった場合、会社に対する処分を決める上で、事案の悪質性の程度が考慮されます。この事案の悪質性の程度を判断するときに、調査開始後に労働局等に誠実に対応したかどうかも考慮されると考えられます。
労働局等からの連絡等があった場合には、なるべく早い段階から誠実に対応し、不正受給後の情状を良くすることが会社にとって有益です。
また、不正受給をしたつもりがなくても、調査に協力をしなければ申請が不正だったのではないかと疑われてしまう可能性が出てきます。不要な疑いを避けるために調査に協力することが会社にとって有益だと考えます。
いずれにせよ、調査に対応するときには、そもそも自社が不正受給をしたのかどうか、不正受給をしたのだとすればなぜ不正受給をしたのかなどを把握した上で、将来のことも考えて会社にとって最もよい結果となりうる最善策をとっていく必要があります。
上原総合法律事務所の調査への対応方法と弁護士へ依頼するメリット
上原総合法律事務所では
☑ 労働局から連絡が来た。どうすれば良いか
☑ 不正受給をしたのでどうすれば良いか
☑ 誤った申請をしたが、どうすれば良いか
などのお問い合わせを多数いただいています。
このようなお問い合わせに対し、まずはご相談をお受けし、どのような対応をすべきなのかをご案内しています。
労働局等からの連絡が来ていない事案については、会社から自発的に労働局に連絡をすべきかどうかについての判断からご案内します。
具体的にはヒアリングのほか、正式にご依頼いただいた場合には資料等も確認の上、不正受給や不適正受給に当たりうるのかを判断した上、今後の想定される事態と選択肢をお伝えし、最善手をご相談させていただきます。
既に労働局からの問い合わせが来ている事案や、会社から自発的に連絡すべき事案については、まず上原総合法律事務所から労働局等に連絡するとともに、並行して事案の詳細を調査し、誠実かつ正直に回答するとともに、理解してもらうべき会社にとって有利な事情を適切に伝えていきます。
多くの場合、詳細な報告書を作成するとともに、訪問調査や労働局での面談にも立会い、会社にとってよりよい結論となるよう、全力を尽くします。
不正受給をしていない会社については、その旨を労働局等に理解してもらうよう働きかけます。
申請内容に誤りがあり、一見すると不正(故意)のように見えるけれども、実際は過失であるという場合にも、その旨を理解してもらえるように丁寧に説明します。
これらの場合にも、まず弁護士から労働局に連絡を入れた上、ヒアリングや資料の精査等の調査を行った上、報告書や意見書等を作成するのが一般的です。
それらを根拠資料と共に労働局に提出し、さらに対面でも労働局への主張、反論等を行っていくことになろうと思われます。
不正受給をしてしまった会社については、その事実や具体的内容等を誠実に伝えて謝罪するとともに、なぜ不正受給をするに至ったか、会社が置かれていた事情などの経緯等も詳細に伝え、会社にとって有利な事情も理解してもらいます。
このような対応をすることで、不正受給をしていないことを理解してもらったり、一見すると故意のように見えるけれども過失であると理解してもらったり、さらには、不正ではあるけれどもやむにやまれず不正をしたのだと言う背景事情を十分に理解してもらい、返金範囲の縮小、公表の回避、刑事告発の回避等、想定していたよりも軽い結末となった事案等は多数あります。
雇用調整助成金の不正受給でお悩みの方は上原総合法律事務所へ
上原総合法律事務所では、コロナ禍における特例下での雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の不正受給について、令和2年後半からご相談をいただくようになり、令和3年以降は年間約100件にのぼる多数のお問い合わせをいただいております。
関東一円はもちろん、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国の本当に多くの会社、経営者の方からご相談いただいております。
その中で多くの方がおっしゃるのは、ご相談前の「自分1人で悩んでいてとても辛い、夜も眠れない、食欲もない」などの辛さとともに、ご相談やご依頼後の「気が楽になった、眠れるようになった、食べられるようになった。助成金についてはとりあえず弁護士に任せておけば良いと考えることで、仕事にエネルギーを割けるようになった。」などというありがたいお言葉です。
令和2年前半に始まったコロナ禍は、本当に多くの方を苦しめました。その混乱の中でなんとか会社を生き残らせて雇用を守りたいと考えた経営者が誤った判断やミスをしてしまう事は、大いにあり得ることだと考えます。
こんなことなら解雇や倒産をしていたほうがよかった、などと考えてしまうこともあるかもしれませんが、コロナ禍を生き残れたのであれば、不正受給の調査等の苦境もまた、専門家のサポートにより乗り越えることができるのではないかとお考えいただければと思います。
また、仮に再起は難しくとも、公表や刑事告発となれば、その後の人生にも影響が生じてしまいかねないところ、最悪の事態を回避するためにも最善を尽くすべきです。
今、1人でお悩みの経営者の方は少なくないかと思いますが、1人で抱え、悩み続ける必要はありません。
上原総合法律事務所は、助成金の問題の専門家にお任せいただくことで、不正(不適正)受給の問題を解決するのみならず、苦しんでいる経営者の気持ちを少しでも楽にするとともに、経営者の時間と能力を本業に集中させ、会社を少しでも回復させていただきたいと考えています。
上原総合法律事務所では、ご相談に迅速に対応できる体制を整え、丁寧にお答えいたします。
ご相談は上原総合法律事務所へのご来所のみならず、web会議またはお電話によるリモートでのご相談も可能です。
全国からのご相談をお受けしています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら
※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
上原総合法律事務所にご相談いただく際の流れはこちらの記事をご参照ください。