
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
1 お問い合わせ
お電話、メールもしくはLINEでご連絡をください。弁護士とのご相談日程を調整いたします。
即日(※1)のご相談も可能です。
ご来所・オンライン(ZOOM)またはお電話でのご相談が可能です。
※1 弁護士の業務状況によります。
2 ご相談(※2)
弁護士には守秘義務がありますので、ご相談内容が上原総合法律事務所外に漏れることはありません。
疑問点や今後どうすれば良いのかなどを納得がいくまでお聞きください。
ご相談においては、不正受給かどうかを判断し、今後どうすべきかをアドバイスします。
不正受給とは、申請内容が真実と異なるとわかっていながら申請をすることをいいます。
つまり、わざと(故意で)真実と異なる申請をしたという場合です。
不正受給をした場合には、労働局を騙したとして詐欺に当たり得る行為ですので、すぐに誠実な対応をはじめる必要があります。この場合、なぜ不正に至ったのかなどを調査した上で労働局にご報告します。
対して、ご相談時には不正受給かどうかわからない場合もあります。
これには
(1)申請が真実と異なるのかわからない
(2)申請は真実と異なるけれどもわざと(故意)したのか間違ってしたのか(過失)わからない
(3)間違えて真実と異なる申請をした(過失)と思っているが、間違い(過失)とわかってもらえるのか,
わざと(故意)と認定されてしまうのかわからない
という場合があります。
間違って真実と異なる申請をしたのであれば、わざと(故意)ではなく間違い(過失)なのだと労働局に理解してもらう必要があります。
そのため、(1)から(3)に当たる場合には、「申請が間違っているのか」、「どの部分が間違っているのか」、「なぜ間違った申請をしたのか」、の調査が必要です。
なお、もちろん、申請が間違っていなければ何の問題もありません。
※2 ご相談は事前振込制の有料相談で、料金は税込25,000円(1時間まで)です。
3 ご依頼・対応開始
ご依頼いただくことになった場合、契約手続(※3)を経て事件処理を開始します。
上原総合法律事務所は全国の事案に対応しており、実際に全国からご依頼をいただいています。
不正受給だとはっきりしている事案においては、不正の原因等を調べた上で、適切なタイミングで労働局にご報告します。
不正受給かどうかわからない事案については、まず不正なのかどうかを調べ、必要に応じて労働局にご報告します(真実と異なる申請がなかったと判明すれば、労働局へのご報告は不要です)。
※3 契約手続はメール等を用いた電子契約も可能ですので、実際にご来所いただく必要はありません。
よくあるご質問
Q 不正だとどういう制裁があるのですか。
A・・・不正受給の場合、不正の部分だけではなく不正を開始して以降の受給額全額と、その受給額全額の2割、さらに利息の3%を返さなくてはなりません。
また、5年間の助成金の受給禁止、事業所名・役員氏名の公表、刑事告発などのリスクがあります。
ただ、事案に応じてさまざまな場合がありえますので、返金額や制裁の詳細については弁護士にご相談下さい。
Q 過失の場合どうなりますか。
A・・・過失の場合は不正受給にはならず、労働局に過失だと認めてもらえれば、申請を修正し、もらいすぎた部分を返金すれば良いことになります。
ただ、事案に応じてさまざまな場合がありますし、労働局に過失と認めてもらえるかどうかが問題になりますので、返金額や制裁の詳細については弁護士にご相談下さい。
Q 申請担当者は真実と異なると分かっていたけれども経営陣は知らなかった場合、不正受給になりますか。
A・・・原則的に不正受給になると考えられますが、様々なケースがあり得ます。弁護士に事案の詳細をお話いただいてご相談下さい。





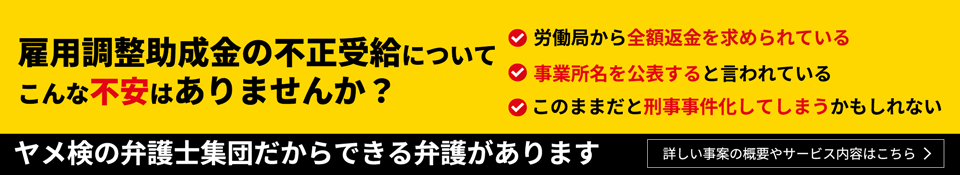
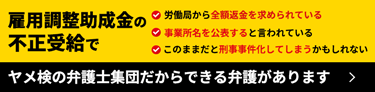
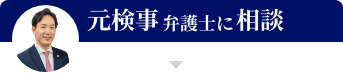
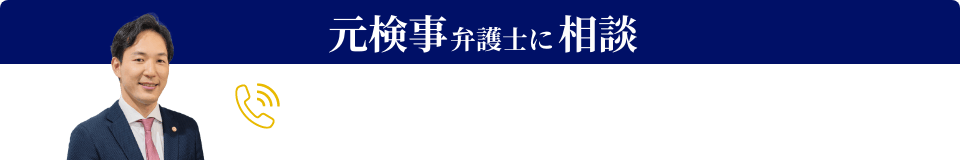
 LINEで
LINEで




