
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
今日、著作権の経済的な価値は高まる一方で、著作権を目的とした取引も活発化しています。
ただ、物理的に存在する動産や不動産を対象とする取引と異なり、目に見えない「権利」である著作権を対象とする取引であるため、紛争が生じることもあります。
そのような争いを防止するためには、著作権譲渡契約の交渉が重要になります。
この記事では、著作権譲渡契約において重要となるポイントを6つに絞り、その具体的な記載例文を説明します。
目次
1. ポイント① 著作物(作品)の特定
まず、著作権譲渡契約で譲渡する対象著作物を特定する必要があります。
著作権とは、著作物(作品)を創作した著作者に対して与えられる権利です。したがって、著作物の名称やタイトル、著作物の種類(例:絵画の著作物、映画の著作物)や内容、著作者名等で著作権を特定することができます。
甲は、本日、甲の有する後記「著作物の表示」記載の著作物(以下「本件著作物」という)の著作権を乙に譲渡する。〈著作物の表示〉
甲製作にかかる絵画美術の著作物である「東京の夜明け」と題する水彩イラスト(縦横各30センチの正方形1枚)。本契約書に縮小カラーコピーを添付する。
題名:「海賊ゴクウの大冒険」
作者:甲
掲載誌:週刊少年フライサンデー
掲載号:令和2年1月1日号~同3年12月10日号
2. ポイント② 権利内容の特定
著作物(作品)を特定したら、次は、その著作物に関するどのような権利が譲渡されるのかを特定する必要があります。
ひとくちに著作権と言っても、著作権法は様々な種類の権利(支分権)を定めており、広い意味では、これら各種の権利がすべて「著作権」という名称に含まれます。
こうした広い意味での著作権について、著作権者は、著作権の全部を譲渡できるのはもちろん、一部を譲渡することも可能です(著作権法61条1項)。
したがって、著作権譲渡契約では、全部譲渡なのか、一部譲渡なのかを明らかにし、一部譲渡のときは対象となる支分権の特定が必要です。
また、全部譲渡のときでも、後述の「翻訳権・翻案権等」と「二次的著作物の利用権」が対象に含まれるか否かは明示する必要があります。
- 【著作権の種類】
- 複製権(著作権法21条)
- 上演権・演奏権(著作権法22条)、上映権(著作権法22条の2)
- 公衆送信権(著作権法23条)
- 口述権(著作権法24条)
- 展示権(著作権法25条)
- 頒布権(著作権法26条) 等
第〇条(譲渡対象の権利)
甲が乙に譲渡する著作権は、本件著作物の複製権及び展示権である。
第〇条(譲渡対象の権利)
甲が乙に譲渡する著作権は、本件著作物に関する全ての著作権である。
3. ポイント③ 「翻訳権・翻案権等」「二次的著作物の利用権」の明示
譲渡対象を著作権の全部とした場合でも、「翻訳権・翻案権等」(著作権法27条)と「二次的著作物の利用権」(著作権法28条)だけは、譲渡対象に含まれているか否かを「特掲」する必要があります(著作権法61条2項参照)。
「翻訳権・翻案権等」とは、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利をいいます(著作権法27条)。平たく言えば、ある著作物に新たな創作を加えて二次的な著作物を作り出す権利です。
例えば論文を翻訳すること、楽曲を編曲すること、造形物を変形すること、小説を脚色すること、戯曲を映画化すること、漫画を翻案する(細部などを作りかえる)ことなどです。
著作者は、翻訳権・翻案権等を専有しているので、自分の著作物を勝手に翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・翻案されない権利があるわけです。
また、二次的著作物に関しては二次的著作物の創作者が著作者として権利を有しますが、もとの著作物(原著作物)の著作者である原著作者は二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同じ権利を有します。このように原著作物の著作権者に認められているのが「二次的著作物の利用権」です(法28条)。
さて、著作権の譲渡契約にあたって、この「翻訳権・翻案権等」と「二次的著作物の利用権」は、これらが譲渡対象であることが「特掲」されていないと、譲渡した者に権利が留保され、譲渡されていないと推定されます(法61条2項。あくまで推定なので、反証することは可能です)。
「特掲」とは、特別に明示して掲載するということです。
特別に明示しての掲載が求められているため、著作権譲渡契約において、単に「全ての著作権を譲渡する」とか、「全ての著作権ならびに将来取得する著作権」と記載するのでは足りず、次のとおり記載する必要があります。著作権法27条・28条という条文を記載することが明確かつ端的です。
第〇条(翻案権・二次的著作物の利用権の譲渡)
甲が乙に譲渡する著作権は、全ての著作権とし、著作権法27条(翻訳権・翻案権等)及び同28条(二次的著作物の利用権)に定める権利を含む。
なお、「翻訳権・翻案権等」と「二次的著作物の利用権」について特掲が要求される趣旨については、様々な見解がありますが、次のような考え方を示す裁判例があります。
「通常著作権を譲渡する場合、著作物を原作のままの形態において利用することは予定されていても、どのような付加価値を生み出すか予想のつかない二次的著作物の創作及び利用は、譲渡時に予定されていない利用態様であって、著作権者に明白な譲渡意思があったとはいい難いために規定されたものである」(東京地裁平成15年12月26日判決※)
4. ポイント④ 著作者人格権の不行使
著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守る権利であり、具体的には、
- 未公表の著作物を公表するか否か、公表するとしてその方法・時期等を決定する権利(公表権:法18条)
- 著作物の公表時に、著作者名を表示するか否か、またどのような名義を付すかを決める権利(氏名公表権:法19条)
- 著作物の内容や題号を無断で改変されない権利(同一性保持権:法20条)
です。
これら著作者人格権は、人格的な利益を保護する権利ですので、著作者に一身専属的に帰属し、譲渡できません(法59条)。
したがって、著作権譲渡契約において「譲渡対象に著作者人格権が含まれる」、「著作権法18条、19条、20条の権利を含む」などと記載しても、譲渡の効力は生じません。
ただ、そうなると、公表権は二次的著作物についても保有しますので、例えば、著作者から二次的著作物の作成・利用に係る法27条・28条の権利も含めて著作権の全部を譲り受けて二次的著作物を創作したのに、これを公表するには、改めて著作者の承諾を得る必要が生じてしまいます。
このような不都合を排除するために、著作者との間の著作権譲渡契約にあたって、実務的には「著作者人格権不行使の特約」を規定することで対応します。
第4条(著作者人格権不行使の特約)
甲は乙に対し、本件著作物につき、乙及び乙指定の第三者に対し、著作者人格権を行使しないことを約する。
この場合、「著作者人格権を放棄する」との文言を記載するケースがありますが、一身専属的な人格的利益である著作者人格権は放棄することができないという見解も有力であるため、疑義を避けるには「放棄」ではなく「不行使」が適切です。
また譲受人だけでなく、譲受人の指定する第三者に対する不行使も明記するべきです。この記載を欠くと、譲受人が作品の翻案などを他者に委託する場合や、乙が著作権を再譲渡する場合に、著作者人格権不行使特約の効力が及ばないからです。
5. ポイント⑤ 著作権譲渡の登録
著作権の譲渡は、法的には譲渡の意思表示だけで成立し、登録などの特別な方式は必要としません。
また、例えば美術の著作物である彫刻作品に対する著作権の譲渡であっても、譲渡の効力との関係ではその彫刻作品の引渡は必須ではありません。
このように、著作権それ自体は目に見えない権利ですから、現在、その権利が誰に帰属しているかは一見して明らかではありません。
そのため著作権には、「二重譲渡」という事態が起こりえます。例えば、著作者である画家Aが、その著作物である絵画の著作権をB出版社に譲渡した後に、コレクターCに譲渡したというケースです。
この場合、先に権利を譲り受けていたB出版社は、自社が著作権者であるとCに主張するためには著作権の移転登録が必要になります。
著作権の移転は、登録しなければ第三者に対抗することができないからです(法77条1号)。この登録制度により、目に見えない「権利」の移転が公示されます。
著作権の登録とは、具体的には、文化庁の著作権登録原簿への登録制度です(著作権法78条、同78条の2・プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律)。
著作権の移転登録は、原則として譲受人および譲渡人が共同して申請する必要がありますが、譲渡人から承諾を得て、譲受人が単独で申請することもできます。
いずれにしても、譲渡人の協力が必要になるので、著作権譲渡契約において、移転登録に関する協力について明記しておくことをお勧めします。
第5条(著作権譲渡の登録)
乙が本契約書で譲り受けた著作権につき、著作権法77条の登録を行うときは、甲はこれに協力する。ただし、登録費用は乙の負担とする。
6. ポイント⑥ 第三者の権利侵害に関する保証条項
著作権の譲渡を受けて著作権を利用した場合に、第三者から著作権等の権利侵害の主張を受けると、場合によっては、せっかく譲り受けた著作権の利用が困難になったり、賠償責任を負うこともあります。
そのような事態を避けるため、譲受人としては、譲渡対象の著作権がすべて譲渡人に帰属していること及び著作物の利用が第三者の著作権等の権利を侵害しないことを保証されるべきです。また、万が一、第三者から権利侵害の主張を受けた場合には、譲渡人の費用と責任でこれを解決することや、譲受人に生じた損害の賠償や紛争解決費用の支払いを規定することも考えられます。
第6条(保証)
甲は、乙に対し、①甲が本契約書記載の譲渡対象である各権利の権利者であること及び
②本件著作物の利用が、第三者の著作権、著作者人格権、著作隣接権その他の権利を侵害しないことを保証する。
7. まとめ
著作権譲渡契約において、一般の売買契約とは異なる、特に注意するべき点を説明しました。
ただし、前述のとおり、著作権の対象となる著作物の範囲は非常に広汎であり、譲渡を受ける著作物の種類ごとに、さらに注意を要する問題があります。
例えば、イラストの著作権譲渡、映画の著作権譲渡、コンピューターソフトの著作権譲渡で、検討すべきポイントが異なることは容易に想像していただけるでしょう。
このように著作権者譲渡契約書の作成にあたっては、法律の専門家からアドバイスを受けることが最善です。

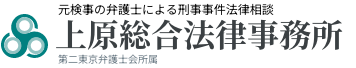





 LINEで
LINEで



