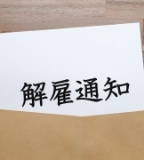無罪を勝ち取りたい

無罪判決を勝ち取るには?元検事の弁護士が刑事裁判のポイントを解説
目次
日本の刑事裁判と無罪判決の現実
有罪率99%以上という数字の意味
日本の刑事裁判では、起訴された事件の有罪率は99%以上とされています。
これは「日本の裁判所が厳しすぎる」というよりも、検察官が「有罪を立証できる事件だけを起訴している」ことの裏返しです。
一方で、検察が起訴した事件でも無罪判決が出るケースは毎年一定数存在しており、決してゼロではありません。
この記事では、元検事(ヤメ検)の弁護士が、刑事裁判のルールや流れ、無罪判決を獲得するための公判における弁護活動のポイントなどを解説します。
「無罪」と「不起訴」の違い
よく「無罪」や「無実」と混同されがちな言葉に「不起訴」があります。
- 無罪判決:起訴された後、刑事裁判において、裁判官が「被告人が起訴された犯罪をしたとは認定できない」と判断した判決。
- 不起訴処分:起訴される前に、検察官が「裁判にかけても有罪立証が困難」「有罪立証はできるけど刑事罰を与えるまでの必要はない」などと判断して裁判にしない処分をするもの。
また、「無実」と「無罪」も厳密には異なり、真に犯罪をしていない「無実」ではなくとも、裁判で検察側が立証できないがために「無罪」となることはありえます。
被疑者にとっては、裁判そのものが避けられる「不起訴」のほうが負担が少なく、「前科」もつきません。
したがって、自分は犯罪を犯していない「無実」だという場合には、捜査を受けている段階で不起訴を目指すことがまず第一で、それでも起訴されてしまった場合に「無罪判決」を目指す流れとなります。
刑事裁判のルールを理解することが第一歩
推定無罪の原則
国際人権規約や日本国憲法にも基づく大原則です。
「疑わしきは被告人の利益に」——つまり、「有罪か無罪か分からない」のであれば「無罪」と判断されるのはもちろん、「合理的な疑いを容れない程度」に有罪の立証がなければ無罪となるのが刑事裁判のルールです。
いかに起訴されれば99%以上が有罪となるとしても、有罪の証明がなされるまでは無罪と推定され、立証がされない限り被告人に有利な判断となるのが大原則です。
証明責任は検察官にある
被告人や弁護士が「無罪を証明」する必要はなく、検察官が有罪を合理的な疑いを超えて立証できなければなりません。
とはいえ、実際の裁判では、検察側の立証に対する反証はもちろん、無罪だという主張立証をしてゆくべき場合がほとんどでしょう。
刑事裁判の大原則であるルールは前提としつつも、無罪判決を獲得するためにはできることは全てやっておくべきです。
「合理的な疑いを容れない程度」とは?
耳慣れない表現かと思いますが、「本当に有罪なのか?」という「合理的」な疑いをさしはさむ余地がない程度に立証されていることが必要という意味です。
例えば、目撃証言が一人だけで、その証言に不自然な点があるなど信用できない場合や、物的証拠と食い違う場合などは目撃証言が正しいのか、ひいては被告人による犯行なのかについて「合理的な疑い」が残るでしょう。
他方で、「疑い」はあくまで「合理的」なものである必要があり、「DNA型も指紋も全く同じ別の人間がいるかもしれない」といったレベルになりますと、天文学的な数字では可能性がゼロではなくとも、もはや「合理的な疑い」とは評価されないでしょう。
裁判で主張立証が尽くされた上、合理的な疑いが残る場合は被告人は無罪となります。
繰り返しになりますが、「無罪であること」を立証するまでの必要はありません。
刑事裁判のおおまかな流れとポイント
1.冒頭手続
起訴状朗読や罪状認否が行われます。
ここで「無罪」を主張することが出発点となります。
事案によっては、公訴事実(その裁判で検察側が立証する事実)のどの部分を争うのか、どのように争うのかの検討も重要となってくることもあり、予め刑事事件に精通した弁護人と検討等を行っておくことが重要です。
罪状認否では被告人の意見のほか、弁護人としての意見を述べることもあり、そこで法的な主張をする場合もあります。
2.検察官の立証
書証や物証(供述調書、防犯カメラ映像など)や証人尋問で立証していきます。
書証については、まず「同意」か「不同意」かの意見を述べ、「不同意」としたものについては検察側は証人尋問等の方法で立証していく必要が出てきます。
検察側の証拠にも、無罪獲得のために有用な内容も含まれている場合もあるため、どの証拠のどの部分を不同意にするかなどは戦略的な検討が不可欠です。
また、検察側の証人の尋問では、弁護人も反対尋問を行います。
そこで証言の矛盾をついたり、あるいは検察側の尋問に異議を申し立てたりすることも重要な弁護活動です。
3.弁護側の立証
- 証拠・証言の信用性を争う
検察側の証拠や証言の信用性を低くする(これを「弾劾」と言ったりします)ための証拠を提出することもあります。
例えば、検察から証拠の任意開示を受けた上、裁判における証言と矛盾する証拠や供述調書等あれば、それを弾劾のための証拠として請求することがあります。
また、もし捜査段階で虚偽の自白をしてしまっているような場合には、取調べの録音録画を精査するなどして、取調べの問題点を指摘するとともに、虚偽の自白であるといえる根拠を主張するなどの弁護活動も必要になってきます。
- 独自の証拠を提出する
被告人の無罪を推認させる、あるいは検察のストーリーと矛盾する独自の証拠を弁護側から提出することもありえます。
「実はアリバイがあった」などといったドラマのような展開は滅多にあるものではありませんが、故意がないことを示すやりとりがスマホに残っていたりなど、あらゆる可能性を模索した上、有用な証拠は積極的に提出していくべきです。
- 被告人質問で供述を補強する
刑事裁判では、被告人自身が弁護人や検察官、さらには裁判官からも質問される場面があります。
弁護人からの質問においては、無罪であることが裁判官に伝わるよう、また矛盾等があるのではないかという疑義が生じることがないよう、的確な質問をして正しい事実を法廷で明らかにする必要があります。
また、検察官からの反対質問や裁判官からの質問を想定しておくことも重要であり、この点は検察や裁判所の考え方を熟知している弁護人からのアドバイス等が非常に有益と考えられます。
4.論告・弁論
検察官が「論告・求刑」、弁護人が「最終弁論」を行います。
弁論はあくまで弁護人の意見でありそれ自体は証拠ではありませんが、無罪獲得のために非常に重要です。
同じ証拠関係であっても、それらをどのように見るかによって、どんな事実があったと認定されるかは変わったものになりえます。
検察としては同じ証拠を前提に「有罪と認定できる」という内容の「論告」をしてきます。
弁護側としては、検察の「論告」の弱点や論理の飛躍等を指摘するとともに(事前に論告の内容が分かるわけではないので、この場面でも、検察の考え方を踏まえ、検察がどのような論告をしてくるか的確に予想することが重要になってきます。)、弁護側のストーリーが事実であると裁判官を説得する論理的な内容の弁論を行うことが不可欠です。
5.判決
裁判官が有罪か無罪かを判断します。
控訴するかなどの検討のためには、判決の内容がどのようなものなのか、指摘すべき問題点があるのかなどの把握・検討も必要になってきます。
6.上訴審
一審判決が有罪であっても、控訴審・上告審で逆転無罪となるケースもあります。
一般的にはより狭き門にはなりますが、一審の判決に明らかな事実誤認や論理の飛躍等がある場合には控訴審等で逆転するケースもありえます。
7.補償等
以下の補償等を受けられる可能性があります。
- 刑事補償手続 → 身柄拘束に対する補償
- 裁判費用補償手続 → 裁判に要した費用の補償
- 国家賠償法による損害賠償請求 → 捜査機関等の違法行為で被害を受けた場合
無罪を勝ち取るための弁護活動の具体例
公訴事実・証拠の徹底検討
検察官の主張や証拠を一点一点検証して、そもそも検察官の主張する事実関係に不自然・不合理な点がないかや、検察側の証拠では犯罪の事実が立証できないのではないか、という検討を行ったり、証拠の矛盾点などを突きます。
これは漫然と証拠を見ているだけで可能なものではなく、最終的に立証の対象となる公訴事実の正確な理解はもちろん、どの証拠からどのような事実を証明しようとしているか、証明される事実からどのような事実を推認しようとしているかなど、検察や裁判所の事実認定の考え方等も踏まえた検討が必要ですし、検察の立証の構造を把握した上、その弱点を的確に見抜くことが重要です。
反対尋問で証人の信用性を崩す
証人の信用性を崩すことができれば、検察官がその証言によって立証しようとしていた事実を証明することができなくなります。これにより、ひいては「合理的な疑い」が生じ、裁判官は有罪とできなくなります。
反対尋問も、漫然と証言に疑問を投げかけるだけではむしろその信用性を増強するだけに終わってしまいます。
事前にその証人の供述調書(検察官の請求する証拠だけではないかもしれず、捜査機関に対しその他の証拠の開示等を求めるべき場合もあるでしょう。)からストーリーを把握して裁判での証言内容も予測した上、その内容に矛盾がないかや証言と矛盾する証拠がないか、されにそれらの不合理な点や矛盾をどのように指摘するのが効果的であるかなども検討しておかなくては効果的な反対尋問はできません。
違法収集証拠の排除
強制捜査の令状が不適切だった場合や、違法な取調べで得られた自白は証拠から排除されます。
証拠の収集方法等に違法があるといった事態は滅多にあるものではないですが、捜査段階で強権的な取調べを受け、耐えきれず虚偽の自白をしてしまったという事例はままあります。
日本の刑事裁判では、被告人の供述調書も非常に重視されているのが実情であり、虚偽の自白に沿った供述調書が証拠として請求されていれば、まずはその排除や信用性の弾劾が必要不可欠です。
具体的には、まずは取調べの録音録画の開示を受けた上、取調べ状況に指摘しうる問題等があるかの精査を行う必要があります。
その上で、問題を指摘するとともに、虚偽の自白をしてしまったのだと裁判官に理解してもらうための証拠の提出、主張をしていかなくてはなりません。
弁護側証拠の提出
ご本人に事実関係を確認したうえ、想定されるアリバイ証拠、防犯カメラ映像、第三者証言などがあれば、それらを独自に収集した上、有用なものは証拠として提出する場合もあります。
日本の捜査機関の証拠収集能力は目を見張るものがありますが、その立場ゆえに捜査は「有罪を立証する」ための証拠収集に偏りがちです。
だからこそ、被告人にとって有利な証拠が見過ごされないよう、適切に収集して裁判で提出する必要があります。
また、検察が持っている証拠の中に被告人にとって有利になりうる証拠が紛れていることもしばしばあります。
証拠の収集のみでなく、評価という観点でも捜査機関はバイアスがかかったものになりがちですし、被告人に有利な証拠に気付いていてもあえてそれを証拠として提出することもないでしょう。
また、弁護側がなにもしなければ、検察側は検察が請求する証拠以外は開示しませんし、裁判で提出されない証拠は裁判官の目に触れることもありません。
そのような、捜査機関が収集していながらそのままでは「なかったもの」として扱われてしまう有利な証拠について、開示請求をするなどして収集し、裁判で提出していくことも重要な弁護活動です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 無罪判決が出たら「前科」はつきますか?
→ いいえ。無罪判決は「犯罪をしていない」という判断ですので、前科は残りません。
Q2. 無罪になった場合、補償は受けられますか?
→ はい。「刑事補償制度」等により補償が認められることがあります。
Q3. 家族が逮捕された直後に弁護士へ相談しても意味がありますか?
→ むしろできるかぎり早期に相談いただくことが重要です。捜査段階での弁護活動が、その後の不起訴や無罪の可能性を大きく左右します。
元検事の弁護士の強み/当事務所の実績
当事務所には元検事出身の弁護士が複数在籍しています。
検察官の立証パターンや裁判戦略を熟知しているため、相手の弱点を突いた効果的な弁護活動が可能です。
また、刑事裁判の経験も豊富に有しており、裁判官の考え方や事実認定等のポイントも踏まえた弁護活動を行っていきます。
上原総合法律事務所では、以下の事案で無罪を獲得しています。
1.不正競争防止法違反
(1)事案の概要
ふるさと納税の返礼品として県外産の商品を地元産と思わせる箱に入れて送ったことが産地の偽装に当たるか問われた裁判で、裁判所は「箱の表示に原産地を示す意味合いは認められない」などとして無罪を言い渡しました。
(2)解説
本件は、検察官が、犯罪にならない事案を誤って起訴してしまった事例です。
そもそも不正競争防止法などの特別刑法は専門性が高く、専門的知識や経験がないと「犯罪成立に必要な要件は何なのか」「どのような事実であれば要件を満たすのか(犯罪が成立するのか)」「どのような証拠であればその事実が立証できるのか」について正確な見通しを立てることが困難です。
そのため、無罪になる可能性があるのに、その可能性に気づかず、無罪をとれたはずの事案で有罪になってしまっているというケースも存在すると思われます。
当事務所で取り扱った上記の無罪事案では、検察官が主張する事実関係では、そもそも犯罪の成立に必要な「原産地・・・を誤認させる表示」とはいえず、およそ犯罪が成立しないのではないか、ということに着目し、この観点から争ったことで無罪を勝ち取った事案です。
担当弁護士:崎川一記(他事務所の弁護士と共同受任)
2.横領
(1)事案の概要
Aさんは、ネット上のコミュニティで知り合った人物Xから「報酬をもらえる」と言われ、自宅に届いた品物を売って換金しました。
しかし、実際にはその品物はYという人物の名義で被害会社からレンタルされたものだったのです。
Aさんはそうとは知らず被害品を売ってしまったのですが、当初、被害品をだまし取ったという詐欺の共犯として逮捕され、最終的には、Xと共謀して被害品(レンタル品)を売ったことが横領に当たるとして起訴されました。
裁判では、被害品がレンタル品とは知らなかったAさんに横領の故意や共謀があるかが問われ、裁判所は、Aさんには横領の故意も共謀も認められないとして、無罪を言い渡しました。
(2)解説
「レンタル品とは知らなかった」のであれば、横領罪の故意は認められません。しかし、Aさんは、繰り返し厳しい取調べを受ける中、認めれば不起訴になるのではなどとの思いから、「レンタル品と知っていた」と虚偽の自白をしてしまい、供述調書が作成されていました。
また、Aに被害品を発送したYの、「Aに送った被害品には、レンタル品であることが分かるシールが付いていた」旨の供述調書も作成されていました。
そのため、本件で無罪を獲得するためには、Aさんの自白調書は信用できないと判断してもらった上、Yの供述も信用できず、Aさんがレンタル品と分かるような事情は認められない、ということ裁判所に理解してもらう必要がありました。
そこで、本件の証拠を徹底的に分析したところ、取調べの録音録画映像から、検察の取調べで黙秘権の告知がなされず、しかも、自白すれば不起訴になると誤解させるような発言がなされていたなどの問題があったことが明らかになりました。
また、Yについても、任意開示されたYのスマートフォン履歴から、供述調書の内容と明らかに矛盾するような客観証拠が存在することも分かりました。
そこで公判では、Aさんの供述調書は、違法な取調べの結果なされた内容虚偽のものであると主張しました。その結果、検察はAさんの供述調書を撤回し、虚偽の自白は裁判で証拠とはなりませんでした。
また、Yの証人尋問では、Yの証言は客観証拠と矛盾していることなどを突きつけ、判決ではYの証言は信用できないと判断されました。
本件は、無罪獲得のために重要な「公訴事実・証拠の徹底検討」「反対尋問で証人の信用性を崩す」「違法な証拠の排除」を丁寧に行った結果、無罪を勝ち取った事案です。
担当弁護士:濱雄治(主任)、崎川一記
まとめ:無罪判決を目指すには「早期の弁護士相談」が鍵
- 日本の刑事裁判は有罪率99%以上
- それでも無罪判決は毎年一定数存在する
- 捜査段階含めなるべく早期の弁護士介入が不可欠
- 無罪を勝ち取るには「証拠の精査」「反対尋問」など、刑事裁判はもちろん検察・裁判所の考え方なども熟知した経験豊富な弁護士による徹底した公判弁護が重要
刑事事件でお困りの方は、一刻も早く弁護士にご相談ください。
当事務所は元検事を中心とした弁護士集団として、迅速かつ的確にサポートいたします。

弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。







 LINEで
LINEで