
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
解雇とは、使用者による労働契約の解約です。労働者の解雇には、いくつかの種類があります。
この記事では、普通解雇とは何か、どのような理由に基づき行うことができるのか、解雇が無効とされる場合とは等、普通解雇をめぐる基礎的な知識について説明します。
目次
1. 普通解雇とは
解雇にはいくつかの種類がありますが、普通解雇とは、どのような解雇を指すのでしょうか。
他の解雇との違いから説明しましょう。
1-1. 普通解雇
普通解雇とは、労務提供の不能、労働能力又は適格性の欠如等を理由としてなされる解雇です。つまり、
労働契約で合意したとおりの義務を労働者が果たさないときになされる解雇といえます。
懲戒解雇と異なり、労働者に対する制裁的意義は有しません。
1-2.懲戒解雇・諭旨解雇
一方で、使用者が企業秩序を維持するために労働者に課す制裁である、懲戒処分としての解雇があります。一般的には、就業規則等に懲戒解雇・諭旨解雇として明記されています。 懲戒処分としての解雇の有効性については、権利の濫用に当たらないかが厳しく審査されます。懲戒解雇の場合、通常は解雇予告や予告に代わる解雇予告手当(労働基準法20条)の支給のない即時解雇となり、退職金も全部又は一部が支給されません。
諭旨解雇は、非違行為があった労働者に対して退職届の提出を勧告し、即時退職を求めるものです。退職金は全額又は一部が支給されるか、自己都合退職どおりに支給されることが多いようです。
1-3.整理解雇
整理解雇は、企業運営の合理化又は整備のために必要な人員削減を理由とする解雇です。
整理解雇は労働者の責めに帰すべき事由によるものではなく、使用者の経営上の理由による解雇である点が特徴です。
2. 普通解雇の要件
2-1. 使用者の解雇の自由は大幅に制限されている
普通解雇によって労働契約を有効に終了させるには、一定の要件を満たす必要があります。
民法上の原則として、使用者には解雇の自由があり、期間の定めのない労働契約は、理由の如何を問わず、いつでも労働契約を解約することができるとされていますが(民法627条1項)、判例・立法により、労働者保護の観点から、この原則は大幅に修正されています。
2-2. 解雇権の濫用
解雇が客観的な合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、
解雇権の濫用として無効となります(労働契約法16条)。
そして、この合理性、社会的相当性は、裁判所によって厳しく審査されるため、現実には、原則と例外が逆転しており、解雇は容易には認められません。
2-3. 労働基準法の解雇制限・禁止規定
解雇には、原則として、30日前の解雇予告又は予告に代わる予告手当の支払いが義務付けられます(労働基準法20条)。
また、業務上の傷病による療養期間とその後の30日間、産前産後休職期間とその後の30日間は解雇が禁止されています(労働基準法19条)。
2-4. 各種法令による差別的解雇の禁止
解雇が、各種の法令によって禁止される差別的な取扱いに該当する場合は、当該解雇は認められません。
例えば、次のような場合です。
・国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱い(労働基準法3条)
・労働組合員であることを理由とする不利益取扱い(労働組合法7条)
・性別を理由とする差別的取扱い(男女雇用機会均等法6条)
・労働基準監督官に法違反を申告したことを理由とする不利益取扱い(労働基準法104条等)
・育児介護休業法上の権利行使を理由とする不利益取扱い(育児介護休業法10条等)
他にも数多くの差別的な解雇が禁止されています。
3. 普通解雇の理由となるもの
一般に、普通解雇の解雇事由として挙げられるのは、以下のようなものです。
①能力不足
②成績不良
③ケガや病気(私傷病)で、当初の契約どおりに働くことができない
④協調性がなく、他の従業員と円滑に仕事をすることができない
⑤遅刻、早退、無断欠勤が多い
普通解雇事由に該当する場合においても、常に解雇が有効となるわけではありません。解雇の有効性判断にあたっては、解雇の理由が合理的か否か、また解雇することが社会的に相当か否かが審査されるのです。
4. ケガや病気(私傷病)による就労の不能を理由とする普通解雇
ケガや病気(私傷病)によって就労できなくなった場合は、労働契約上の労務提供義務に違反しますから、普通解雇の理由となります。
もっとも、ケガや病気(私傷病)を理由として解雇する場合、次のようなケースでは、解雇権濫用と評価される可能性があります。
・私傷病休職制度が設けられているのに、これを利用させないで解雇した
・回復の可能性があることを考慮しないで解雇した
・軽減した業務に従事させる等の解雇回避措置をとらないで解雇した
5. 能力不足を理由とする普通解雇
使用者は、労働者に一定の労務提供をする能力があることを期待して労働契約を締結しているのですから、契約上予定された労務を遂行する能力に欠けることは、普通解雇の理由となります。
ただし、労働契約上、職種が狭く限定されている場合以外は、どのような能力を期待されていたのかが問題となり、能力の有無は使用者によって恣意的に判断される危険もあります。
能力不足による解雇が有効か否かは、その能力不足が債務不履行といえるのかどうか、契約を継続できないほどの事由に該当するのか、という観点から判断されます。
例えば、能力不足を理由とする解雇の有効性が問題となった裁判例として以下のものがあります。
東京地判平成12年4月26日・プラウドフットジャパン事件・労働判例789号21頁
Xは、コンサルティング・サービスなどを業とする外資系企業であるYに、インスタレーション・スペシャリスト(以下「IS」)として中途採用され、Yとの問に期間の定めのない雇用契約を締結(年俸七七〇万円)しました。その後、YはXに対し、職務遂行能力を欠くとして、解雇する旨の意思表示をしました。これに対しXが本件解雇は就業規則が定める解雇事由に当たらず、解雇権の濫用として無効であると主張し、労働契約上の地位確認と賃金の支払いを求めました。
判決は、XのISとしての能力及び適格性について、Xは平成7年4月10日にYに雇用された後、同年6月6日から平成8年9月27日までの間に五つのプ口ジエク卜に従事してきたが、そのうちの一つを除くプ口ジエクトにおいて、ISとして求められている能力や適格性の点においていまだ平均に達していない状態が入社以来1年半にわたって断続的に続いてきたのであり、「今後もXを雇用し続けてISとして求められている能力や適格性を高める機会を与えたとしても、能力や適格性の点において、Xが平均に達することを期待することは極めて困難であった」としました。そしてこの事実は前記就業規則の解雇事由に該当するとしました。
さらに判決は、YはXをプ口ジエクトから外した後に、Xに対し別の職務を提供して雇用を継続しようとする提案をし、Xとの間でその後約3か月間にわたる交渉を重ねたものの、妥協点を見出すことができず、さらに交渉が中断してから2か月余りが経過した平成9年3月12日に至って本件解雇に及んだという経緯を併せ考えると、本件解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができないということはできず、権利濫用には当たらないとしました。
6.協調性不足を理由とした解雇
職場は複数の労働者が共同して労務を提供する場ですから、他の労働者との共働を円滑に行うための協調性を備えることは、労務提供能力の重要な一部と言えます。
したがって、労働者が協調性を欠く場合、一種の労働能力欠如と位置づけることができ、普通解雇の理由となります。
ただし、協調性の有無・程度の判定は使用者によって恣意的に判断される危険がありますし、協調性は特定の人間関係の中で問題となるもので、その他の労働者との関係では協調できる可能性もあります。
そのため、裁判例では、①実際の業務や企業秩序に現実的な影響を与えたか否か、②配置転換や注意・指導等による改善の機会を与えたうえで解雇がなされたかが重視されています。
例えば、協調性不足を理由とする解雇の有効性が問題となった裁判例として、以下のものがあります。
東京地裁平成24年7月4日判決・トレンドマイクロ事件・労働経済判例速報2155号9頁
Yが周囲との協調性が欠如していること等を理由としてXを解雇した事案で、裁判所は、①XにはYが求める協調性が欠けているとしたうえで、②Yによる再三の注意指導にもかかわらずXが姿勢を改めなかったこと、③Yが解雇回避措置として他部署への異動を打診しても、Xが「この会社あほ???」と述べる等これをあざ笑うかのような不誠実な態度をとり続けたこと、④Yは退職勧奨を行ったうえで解雇を実施していること、⑤YとXは長時間かけて協議をしてきたこと等から、本件解雇は社会通念上相当であるとして、解雇を有効と判断しました。
7. 普通解雇と退職金
多くの企業で、退職金規程に、懲戒解雇の場合には退職金を不支給・減額とする旨の規定を設けていることが多いと思われます。
もっとも、退職金の不支給・減額規定については、そのような規定も有効としつつ、退職金が功労報償的な性格を有していることから、過去の勤続の功労を抹消・減殺してしまうほどの重大な非違行為があった場合に限定して適用できると考えるのが一般的です。
普通解雇の場合は、このような退職金を不支給・減額とする条項は定められていないことが通常です。退職金規程に定められた支給要件を満たす限りは、普通解雇であっても退職金が支給されます。
8. 普通解雇が無効となった場合
普通解雇が解雇無効となった場合には、労働契約は存続し、労働者は労働契約上の権利義務を失いません。
使用者は、労働者に対し、無効な普通解雇によって就労できなかった期間中の賃金を支払う義務があります(民法536条2項)。
また、労働者が、違法な解雇によって精神的苦痛を受けたとして、会社に対して不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求する事例も多くみられるようになりました。
しかし、解雇が無効であると判断されたとしても、当然に使用者が不法行為の要件を充足するわけではないため、むしろ損害賠償請求が認容されるのは例外的な場合です。
有効でない解雇の不当行為該当性について判断したものとして、懲戒解雇(諭旨解雇)の事案ですが、以下の裁判例があります。
静岡地判平成17年1月18日・静岡第一テレビ事件・労働判例893号135頁
裁判所は、懲戒解雇が不法行為に該当するというためには、使用者が行った懲戒解雇が不当、不合理であるというだけでは足らず、以下のような場合に該当することが必要であるとしています。
- 懲戒解雇すべき非違行為が存在しないことを知りながら、あえて懲戒解雇をしたような場合
- 通常期待される方法で調査すれば懲戒解雇すべき事由のないことが容易に判明したのに、杜撰な調査、弁明の不聴取等によって非違事実(懲戒解雇事由が複数あるときは主要な非違事実)を誤認し、その誤認に基づいて懲戒解雇をしたような場合
- 上記のような使用者の裁量を考慮してもなお、懲戒処分の相当性の判断において明白かつ重大な誤りがあると言えるような場合
9. 普通解雇の使用者側のメリット、デメリット
・問題のある労働者を職場から排除して、生産性の向上が期待できます。
・懲戒解雇よりも労働者に有利な扱い(退職金支給等)をするため、労働者の納得を得られやすい傾向にあります。
・労働者の意に沿わない場合、解雇無効を主張され、訴訟等に発展する危険があります。このリスクを考えると、問題のある労働者でも、解雇という手段ではなく、説得を試みて、退職金の支給と引き換えに、自ら退職してもらう(退職届を提出させる)方が無難と言えます。
・解雇無効と判断された場合、バックペイ(解雇期間中の賃金相当額)や、事案によっては慰謝料の支払までも命じられる危険があります。
10. 普通解雇の手続きの流れ
①事実の調査
本人及び周囲の労働者からのヒアリング等により、普通解雇の理由となる事実があるかどうか調査を行います。
②法的有効性の検討
調査結果につき、普通解雇事由に該当するか否か、解雇の合理的理由・社会的相当性を満たすか、解雇禁止、差別的取扱い禁止等の法令違反に該当しない等、法的有効性を検討します。 非違行為の場合、懲戒解雇、諭旨解雇とするか、普通解雇にとどめるかも検討し、方針を決めます。
③労働組合や労使委員会との協議等の解雇手続が定められていれば、これを履践します。
④本人に対し、解雇日の30日前に解雇予告を行います(又は解雇予告手当に相当する30日分以上の平均賃金を支払います)。事実関係を明確にするため、解雇日と解雇理由を明記した解雇通告書を交付することが望ましいでしょう。なお、使用者は、労働者の請求があれば、解雇理由等を記載した証明書を遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条)。
11.まとめ
普通解雇とは言っても、解雇の有効性は厳しく問われます。
普通解雇を検討する場合には、労働問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

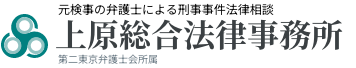


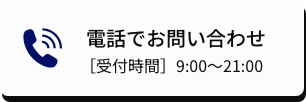


 LINEで
LINEで



