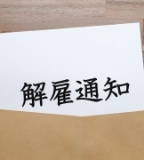当局・マスコミ対応

社内不正・コンプライアンス違反発覚時の当局・マスコミ対応と実務上のポイントを元検事の弁護士が解説
目次
はじめに:社内不正等が発覚したとき、企業がまずとるべき行動とは?
「従業員による不正行為が発覚した」「マスコミから取材を受けて初めて不正を知った」——
こうした状況に直面したとき、企業にとって最も重要なのは「初動対応」です。
社内不正やコンプライアンス違反が明るみに出た際、対応を誤ると、行政処分や刑事責任、取引停止、企業価値の毀損といった重大なリスクにつながります。さらに、報道機関やSNSによる情報拡散が、企業ブランドに長期的な打撃を与えることもあります。
本記事では、不正発覚後の初動対応、当局やマスコミへの対応、調査委員会の設置、処分や再発防止策の立案まで、実務上の重要ポイントを徹底解説します。
1. 初動対応の重要性
不正やコンプライアンス違反が疑われる段階から、迅速かつ適切に法的リスクを最小限に抑える行動が求められます。
事実関係の把握
まず行うべきは、発生した不正行為等の全体像の把握です。
【よくある質問:どのように事実確認を進めるべきですか?】
- 内部通報や報道の内容を確認
まずは、把握した不正等の恐れがある情報について、事実確認をするために内容をつぶさに確認する必要があります。
具体的に、誰が、いつ、どのような行為をした可能性があるのか。そして、それが真実である場合どのような問題が生じるのかを検討する必要があります。
これを怠ると、のちの証拠収集や関係者への聞き取りでどのような内容を聞き取るべきかという軸がぶれてしまい、効果的な調査ができなくなってしまいます。 - 関連資料・データの収集
収集すべき資料等を検討しつつ、一刻も早く当該関連資料の収集に努めるべきです。
それぞれの証拠は時間が経てば経つほど散逸(証拠がなくなってしまったり、関係者の記憶が減退してその証言等が得られなくなること)してしまいます。
特に客観的な証拠は、一度収集すれば改変等は難しく、記憶のように減退するものではありませんが、収集できずに失われた場合は二度と収集することはかないません。幅広い証拠を迅速に収集し、保全する必要があります。
初動段階での証拠保全は、後の調査・当局対応・裁判対応に不可欠です。
メール、チャット、各種ファイルなどのデジタルデータのバックアップ、防犯カメラの映像や勤怠記録の保全、関係者の社用パソコン・スマホの利用制限や回収(法的リスクにも配慮する必要があります。)などの対応が必要になるでしょう。
※証拠保全の方法については、弁護士の関与が推奨されます。違法な調査やプライバシー侵害は、逆に企業の法的リスクとなる可能性があります。 - 関係者への聞き取りの実施(証拠隠滅を避けるため、計画的かつ段階的に)
不正関与の可能性がある従業員や関係者へのヒアリングは、調査における必須のプロセスです。
通報等された事実や客観的証拠関係から、不正等の事実に関与している可能性がある者や不正等の事実を知っている可能性がある者に対してヒアリングを行うことになります。
しかし、ヒアリングを受けたものがその事実を第三者に漏らしてしまい、それによって関係者による証拠隠滅等が行われる可能性があります。
したがって、ヒアリングを行う順番やタイミングはよく検討する必要があります。
また、ヒアリングの際、対象者が最初から正直な話をするとは限りません。保身や誰かをかばうためなどで虚偽の話をする可能性が想定される場合には、弁解の内容も推測するなどした上、言い逃れのできないような客観証拠等を準備しておくなどの対策も必要となってきます。
従業員へのヒアリング等を行うにあたり、特に内部通報等をきっかけとする場合などは、通報者の保護やプライバシーへの配慮が求められます。他方で企業内のハラスメントや横領、不正請求といった事案では、調査開始を遅らせることが証拠隠滅のリスクを高めることにもなりえ、迅速さと慎重さの双方が求められる難しい局面です。
2. 当局対応について
社内不正の内容によっては、関係官庁や監督機関への報告が必要となります。この報告を怠ると、行政処分の対象となったり、刑事責任を問われる可能性がありますし、後々問題が公になってから初動対応について問題とされ、バッシングを受けるなどのレピュテーションリスクもあります。
以下では不正受給事案(例:雇用調整助成金等)を例に挙げて行うべき初動対応や当局対応のタイミングについて見てみましょう。
【事例】
従業員の出勤実態があるにもかかわらず、「休業」として雇用調整助成金を申請していたことから、不正受給に該当する可能性があるという事実が発覚した場合。
証拠の収集
助成金の不正受給を調査する場合、当該助成金の申請に用いた証拠書類を収集し、さらにそれと矛盾する証拠がないかという視点から、タイムカード、日報、賃金台帳、有給や遅刻想定の届け出、経費精算に係る書類などの様々な客観的な証拠類を収集した上、これらを精査する必要があります。
たとえば、従業員が休業していたとして申請している日について実際は稼働していたのではないかと疑われる場合には、従業員のタイムカードが打刻された記録がないか、経費申請された領収書等から従業員の勤務を推測できないか、社用車の使用履歴や取引先とのメール等を確認し、業務を行っていたと認められないかなどを確認する必要があり、多岐にわたる証拠資料の収集と精査が必要です。
関係者へのヒアリング
助成金の不正受給の場合には、休業になっていた従業員に対してヒアリングを実施し、休業記録と実際の勤務に齟齬がないかなどを確認することになります。場合によっては経理担当者に対して確認をすることも必要です。
そして、仮に齟齬が存在する場合には、助成金申請担当者や取締役に対して当該齟齬の有無を認識していたかどうかという点をヒアリングするなどします。
当局への報告タイミングについて
助成金については労働局が調査等を行っているところ、当局に対する報告のタイミングを検討する必要があります。
当局は、不正が疑われる事業者に対しては、独自に調査を行っています。
事業主に対して資料を提出させ、当該資料から認定できる事実を前提に、支給決定の取消や公表などのペナルティを課すのです。
しかし、多くの場合彼らは警察等の捜査機関とは違って調査のプロではないため、証拠の見方や事実認定に不合理な部分がある場合も多くあり、その誤りに当局が自ら気が付くことは困難です。
また、行政の判断は形式的で覆されにくいため、独自調査によって不正受給であると一度判断されてしまった場合には、それが誤った判断であったとしても、覆すのは容易ではありません。
以上を踏まえると、労働局からの独自調査が始まる前に報告をすることが重要になります。
早い段階で当局への報告を行うことはメリットデメリットが存在しますが、いつまでも報告をしないままでいた場合、労働局の独自調査が始まり、不利な判断を下されてしまう可能性があるからです。
したがって、原則としては当局への報告はできる限り早い段階で行うことが望ましいでしょう。
以上のように、助成金を不正受給したような比較的単純な事例であっても初動対応としてすべきことは多岐にわたります。
もちろん、不正の内容によっても対応は千差万別ですし、調査に際して、第三者委員会を設置するべき場合や単に顧問弁護士等による調査で済む場合など様々です。
一口に不正といっても、いち従業員の横領の場合であれば、同従業員の退職、債権の回収、さらには警察への刑事告訴も見据えて調査をする必要がありますし、経営層による品質不正の場合であれば第三者委員会を設置し、調査結果を公にすることで企業価値の毀損をなるべく避ける方向で考えなければいけない場合なども考えられます。
また、不正の発覚により、事業の許認可が維持できなくなる場合もあり、そのことは企業の事業継続に直結します。
例えば、ホテルなどを営む会社の場合、取締役が拘禁刑以上の刑に処せられた場合旅館業許可の欠格事由に該当することから業務自体を行えなくなってしまいます。
先ほど例に挙げた助成金の不正受給も額や態様によっては詐欺罪で立件されてしまい、許認可等を失うこともあり得ます。
しかし、早期に労働局へ報告することで、不正であっても、刑事事件として刑事告発されることを回避できる可能性もあります。
このように、当局への報告は最終的な処分を検討するうえで重要なファクターになりえます。なにか不正等で問題が生じた場合には、最終的な結論がどうなるのかという点を予測し、早期に対応する必要があります。
どのような初動対応及び当局対応をするかは、最終的に個別事例による判断になりますので、専門家等への相談をお勧めいたします。
3. マスコミ対応
情報拡散のスピードが速い現代において、企業の信用を守るためにはメディア対応が極めて重要です。
調査の過程を内部の従業員等がSNSに拡散したり、第三者委員会等での調査を経て記者会見を行ってもその際の発言が一部切り取られるなどして、マイナスイメージが拡散されてしまうことも多々あります。
そういった企業イメージの毀損を防ぐためには以下のような点に注意する必要があります。
情報の内部的コントロール
まず、最も重要なのは、関係者以外への情報の漏洩を防止し、社内の情報統制管理を徹底することです。
そのうえで守秘義務の内容及びそれが破られた場合のペナルティなど、守秘義務等に係る規定の再確認
が求められます。
さらに、ヒアリング自体が不適切な方法で行われた場合(威圧的な方法等)や、そうと受け取られる可能性のあるヒアリングを行えば、SNSなどで暴露されるリスクがあります。
調査に際しては、誰に聞かれても公正であるような調査を心掛け、万が一流出等した場合も想定した適切なヒアリングを実施する必要があるでしょう。
不正確な情報への対策
いくら正確に情報をコントロールしようとしても、事実と異なる報道や情報の拡散がなされてしまう場合もあります。
いわゆるSNS上の炎上現象をみても、適切な情報がないまま一部の憶測や虚偽情報が拡散されてしまい炎上に至る場合も多く見られます。
そのような場合には適切な反論(正しい情報の開示を含む)・修正依頼を徹底することが有効かもしれません。
場合によっては、法的措置(名誉毀損・業務妨害による刑事告訴や虚偽情報を拡散するアカウント等に対する開示請求等)の検討も視野に入れる必要があります。
しかし、昨今では、このような法的措置をにおわせること自体が「スラップ訴訟」(自由な言論を封じる目的での民事訴訟)であるとのそしりを受けることもあるため、実際にどこまでの対応を行うかは、専門家に相談の上、慎重に判断する必要があります。
適切な情報発信
不正確な情報が拡散される前に、自社において適切な情報を発信することも有効な手段のひとつです。そのためにプレスリリースの発行をすることが考えられます。
内容については、法的に誤りがないか、文章に炎上の要素がないかなどを、弁護士や危機管理に関する広報の専門家によって確認をする必要があります。
初動対応においては、「調査中であること」「社内体制を見直していること」などの中立的かつ真摯な表現を行い、不確実な情報を発信しないように注意するとともに、メディアなどからの質問に対する想定問答を用意しておくことも大事です。
4. 調査委員会の設置・調査
不正の性質・規模によっては、調査委員会の設置が企業の説明責任にとって重要となってきます。
より客観性が高いものとしてのいわゆる第三者委員会を設置する方法もあれば会社内部に調査委員会を設置する方法などもあり、その態様は様々です。
第三者調査委員会
多くは弁護士や公認会計士等の外部専門家で構成されており、客観性と透明性が担保されています。最終的には調査報告書を公表することで、企業の信頼回復につながります。
第三者委員会といっても、その客観性や調査・報告の範囲にはバリエーションがあります。
たとえば日弁連が策定したガイドラインに基づけば、第三者委員会の調査対象は、「第一次的には不祥事を構成する事実関係であるが、それに 止まらず、不祥事の経緯、動機、背景及び類似案件の存否、さらに当該不祥事を生じさせ た内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点、企業風土等にも及ぶ」としています。しかし、昨今では調査スコープを限定し、当該不祥事を構成する事実関係のみについて調査をする場合も多くあります。
内部調査委員会
第三者委員会と異なり、企業内のコンプライアンス部門や法務部、顧問弁護士などが中心となって調査を行います。
第三者委員会の設置する場合よりも迅速な調査・初動対応が可能ですし、コストも比較的低いと言えます。
ただし、あくまで内部の調査である以上、調査の信頼性や中立性に疑問が生じやすいと言えます。
状況に応じて、どのような調査手法を用いるのが適切かを十分に吟味することが求められます。
5. 従業員等への処分・再発防止等
不正を行った従業員等への処分
不正を行った従業員に対しては、まずは就業規則に基づく懲戒処分(戒告、減給、懲戒解雇など)が考えられます。
懲戒処分等については、社内の処分とはいえ、公平性と透明性の確保が重要であることは他の変わりません。
損害賠償請求等
従業員による不正行為が行われた場合、損害賠償請求が可能なことがあります。
ステークホルダーに対する説明のためにも民事訴訟の提起が必要な場合もあるかと思いますが、従業員に対する過大な請求は社会的批判の対象にもなり得るため慎重に検討をする必要があるでしょう。
6. 内部通報制度と公益通報者保護法への対応
内部通報制度の意義
不正の早期発見・防止には、社内外に開かれた内部通報制度の整備が不可欠です。消費者庁の調査では、内部通報制度を導入している事業者における不正発覚の端緒の7割超が内部通報によるものとされています。
逆に内部通報窓口の不存在や形骸化は不正の発覚を遅らせ、結局は会社の不利益に繋がる要因になってしまいます。
そのために匿名通報、外部窓口(弁護士等)の活用などにより、通報者のプライバシー保護を徹底する体制を構築し、内部通報窓口を実態のあるものにすることが必要です。
公益通報者保護法のポイント
内部通報を行ったものは公益通報者保護法によって保護されます。
具体的には、通報者に対する解雇や降格等の不利益取扱いの禁止(派遣契約の解除も無効です。)、通報者に対する損害賠償請求の禁止、通報者を探すことや通報を妨害することの禁止など多岐にわたります。
このような保護を与えることで、内部通報を容易にし、企業不祥事の早期発覚、被害拡大の防止につながるのです。
また、その他にも企業に対する内部通報対応の責任者設置や通報対応記録の作成・保存などの体制整備義務が課せられており、これに反した場合は行政措置の対象となることがあります。
また、実務上の注意点として、通報内容の信憑性にかかわらず、丁寧な対応が必要ということはいうまでもありません。
まとめ:社内不正発覚時の対応は「初動」が重要
企業にとって、社内不正やコンプライアンス違反は致命的なリスクとなり得ます。しかし、適切な初動対応と透明性ある情報公開、再発防止への取組を通じて、信頼の回復は十分可能です。
不正発覚時の対応に迷われた際は、弁護士への相談を速やかに行うことが、リスクを最小限に抑える最善策です。
不正対応は企業の命運を左右します。当事務所には元検事の弁護士が所属し、調査や当局対応を多数経験しています。初動に不安を感じる経営者・法務担当者の方は、ぜひご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 不正が内部通報で発覚しました。匿名の通報者に対してどう対応すべきですか?
A. 通報者の特定や報復的措置は禁止されています。通報内容を丁寧に検討し、必要に応じて調査委員会の設置を検討すべきです。
Q2. プレスリリースで不正を公表すべきでしょうか?
A. 上場企業や社会的影響が大きい場合、事実と異なる情報の拡散が懸念される場合などはは公表が推奨されます。内容は法務・広報と連携して慎重に作成してください。
Q3. 不正に関与した社員に刑事告訴は可能ですか?
A. 故意による横領・背任などは告訴可能です。ただし企業の社会的影響や証拠状況を考慮し、弁護士と相談の上で決定すべきですし、犯罪を証明するための証拠収集・保全も重要です。

弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。







 LINEで
LINEで