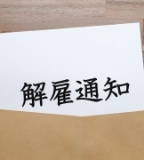解雇や損害賠償をしたい
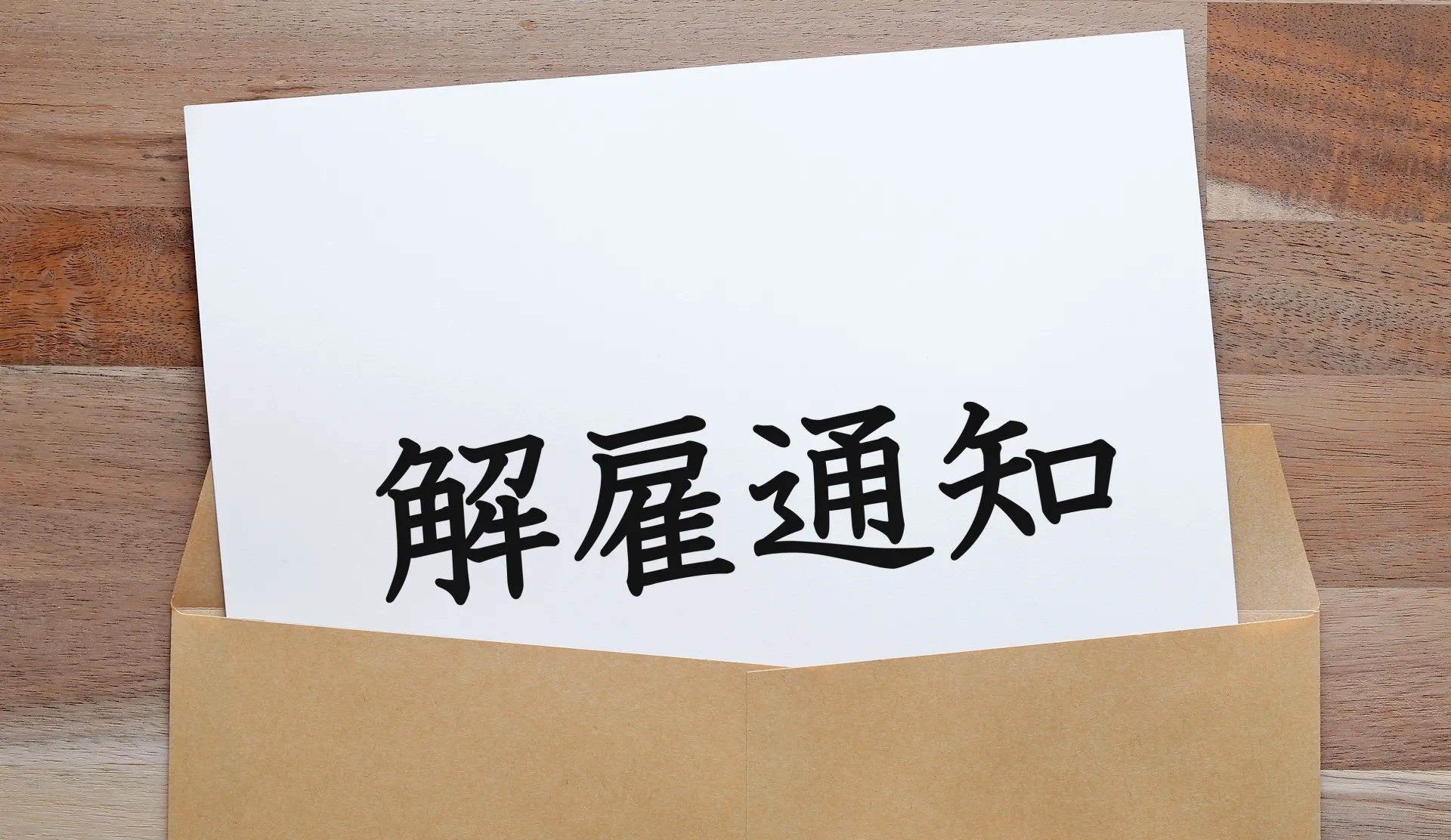
不正・コンプライアンス違反や犯罪を行った従業員に対する解雇や損害賠償請求は可能?元検事の弁護士が解説
目次
不正行為等が発覚したとき、企業がとるべき対応とは
企業活動において、従業員による不正行為やコンプライアンス違反は決して他人事ではありません。横領、情報漏えいやハラスメント、取引先と結託しての架空請求などの行為が発覚した場合、企業としては毅然とした対応が求められます。また、従業員による犯罪行為によっても、風評被害や他の従業員への影響といったリスクもあります。
この記事では、会社側の立場から、従業員による不正行為等が発覚した際に、当該従業員に対してどのような処分が可能か、損害が生じた場合にどのような請求が可能かなど、適切に対応するためのポイントを解説します。
1.まずは事実の確認、証拠収集を
従業員が関与した不正等が疑われる場合、まずは徹底した事実確認、証拠収集が必要不可欠です。
解雇含めた懲戒処分を行うにせよ、損害賠償請求等を行うにせよ、まずは事実関係を正しく把握する必要があるばかりか、争われた場合に不正等があったことを証明するための証拠を収集しておかなくてはなりません。
不正等を行う従業員らは、会社や同僚に発覚しないよう隠ぺい工作を行っている場合も多く、何の準備もせずに当該従業員に話をするなどすれば、事実関係を否認するとともに、せっかくの証拠を隠滅される、関係者と口裏合わせをされるなどして、結局何も明らかにできないといった結末になりかねません。
そうならないためにも、対象従業員には勘付かれないように、請求書や領収証、電子メールやチャットの記録などの客観証拠を予め収集して分析するとともに、信頼できる関係者からのヒアリングを先行し、それも証拠化しておくことなども必要です。
また、いざ対象従業員に直接ヒアリング等を行うという場合には、その際の段取りやその後の業務遂行継続のための体制構築等の備えもしておかなくてはなりません。
いずれにせよ、不正等を明らかにし、適切に対応するためには、専門家のサポートも得た上で入念な準備をしておくことが必要不可欠です。
2.懲戒処分や解雇は可能か
従業員による不正等があった場合、就業規則上の懲戒事由に該当すれば、懲戒処分を行うことができます。
懲戒処分の内容としては、戒告や訓告、減給、出勤停止、降格等がありえますが、その際たるものが懲戒解雇です。
懲戒解雇は言うまでもなく当該従業員を解雇する最も重い懲戒処分であり、解雇予告手当も発生せず、また退職金もその全部ないし一部が支払われないのが一般的です。
ただ、重い処分であり従業員への不利益も大きいことから、解雇が無効であると争われるなどのリスクもありえます。
不正行為等があった場合、懲戒解雇事由として認められるだけの事情と評価されることが多いとは思われますが、きちんと事実が認定できるよう証拠が必要ですし、そもそも就業規則上懲戒解雇等について定めがあることが前提となります。
そのほか、当該従業員を退職させたい場合には、懲戒事由があることを前提に退職を勧告する諭旨解雇や普通解雇もありますが、やはり紛争となるリスクは否定できません。
他方で、不正行為等が発覚した場合、当該従業員もその職場で働き続けることは難しいと感じる場合がほとんどでしょう。
そういった場合、会社側と従業員側の意向はある程度一致してもおり、シンプルに合意の上での自主退職という手続もありえ、最も穏当な手段と言えるかもしれません。
ただ、その場合であっても、実質的には強制的な退職勧奨であったなどと事後的に争われるリスクは否定できないため、適切な手続を行った上、書面化もしておくなど、専門家の助力を得ることが望ましいと考えられます。
3.損害賠償請求のポイント
従業員による不正行為等により会社に損害が発生している場合、「不法行為」として、損害の賠償を求めることもありえます。
雇用契約上の義務(契約上、退職後にも競業避止義務等が課されており、これに違反したといった場合も想定されます。)に違反したとして債務不履行責任を問うというパターンもありえますが、以下では不法行為の場合について説明しています。
不法行為とは、民法第709条に規定されているもので、故意または過失により他人の権利や利益を侵害した者に、その損害を賠償する責任を認めたものです。
損害賠償請求の要件
損害賠償請求を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
権利や利益の侵害:企業は様々な権利などを有しています。会社のお金や財産はもちろん、著作権等もそのうちの一つですが、これらの権利等が害されることが必要です。本来だったら受け取れるはずの報酬を受け取れなくなること等も権利・利益の侵害に該当します。
故意または過失:従業員が故意または過失により不法行為を行ったことを指します。また「過失」はわざとではないが落ち度があるという状態を指します。不正行為等の場合、多くは故意が認定可能であろうとは思われるところです。
損害の発生:企業に具体的な損害が生じたことが必要で、請求のためにはその金銭的な評価も必要です。権利や利益の侵害があったとしても具体的な損害が生じなければ不法行為に基づいて損害賠償を請求することはできません。横領や架空請求などであればある程度明確な金銭的な被害がありえますが、機会の損失などであれば金銭的な評価が困難なことも想定されます。
因果関係:侵害行為と損害との間に因果関係があることが必要です。侵害行為も存在し、損害も生じていても、請求が認められるのはそれらの間に因果関係が証明される場合です。
これらの要件を満たすことを立証するためには、詳細な証拠の収集と分析が不可欠です。
民事訴訟・強制執行という選択肢
対象従業員が不正や責任を認めない場合や、任意での支払い等にも応じない場合、民事裁判により確定判決を得た上で、強制執行という手続で回収するという手段を取ることになります。
民事裁判の流れはおおむね以下のとおりです。
訴訟の主な流れ
1.訴状の作成・提出
損害賠償請求をするには、まず訴状を作成し、被告の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に提出します。請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所、それ以下の場合は簡易裁判所が管轄します。
2.訴状の送達と答弁書の提出
裁判所が訴状を相手方に送達し、被告(加害者側)は答弁書を提出します。答弁書では、請求内容を争うか否か、争う場合の主張を明記します。
3.口頭弁論・弁論準備手続き
裁判は約1か月ごとに期日が開かれ、双方の主張・証拠の提出が進められます。
裁判は公開の法廷で行われるイメージが強い方もいらっしゃると思いますが、実務上は、弁論準備手続という公開されていない場で代理人と裁判官が互いの書面や提出された証拠をもとに主張を整理していくことがほとんどです。主張を整理していく中で、裁判官が心証を開示し(裁判官どっちの言い分が正しいと思っているかを当事者にある程度示すこと)、和解を勧められることもあります。
互いの証拠を出して、裁判官による心証開示を経ても和解がまとまらない場合、証人尋問や本人尋問が実施される場合もあります。
4.判決または和解
証拠調べの終了後、判決が下されるか、当事者間で和解をすることで裁判は終了します。特に損害賠償請求事件では、金額のほか、金銭支払いの条件を調整して和解で解決することも多くあります。
訴訟の提起から終結までは早いもので半年程度、長ければ数年かかるものもざらにあります。
訴訟を提起するか否かは、かかる時間や費用等のコストも十分に考える必要があります。
強制執行について
損害賠償請求が認められ、和解調書や確定判決が得られた場合や、公正証書に強制執行認諾文言が付されている場合、支払いがなされなければ、法的に「強制執行」の手続きをとることが可能です。
強制執行の基本的な流れ
1.債務名義の取得
民事訴訟で勝訴ないし和解した場合は「確定判決」や「和解調書」
公正証書に「強制執行認諾文言」が付いている場合は、その公正証書自体が債務名義となります。
2.執行文の付与申立て
債務名義に基づき、裁判所に対して「執行文」の付与を申立てます。
3.差押え申立て
相手方の財産(預金、不動産、動産など)に対して差押えの申立てを行います。主に地方裁判所での手続となります。
4.差押えの実施と換価
裁判所の執行官が実際に財産を差し押さえ、必要に応じて競売などによって換価されます。その後、回収額が債権者に配分されます。
注意点として、強制執行を行うためには、相手方の財産情報(預金口座、不動産の所在など)をある程度把握しておく必要があります。
金融機関への預金差押えが最も迅速かつ効果的ですが、実際に残高があるとは限らないため、事前調査(資力調査)が重要です。
残念ながら、裁判等で勝訴するなどしても「無いところからは回収できない」というのが実情であり、どこまでの手段を講じるかは、得られる効果を踏まえた判断が必要です。
任意での回収、公正証書の作成等
損害賠償請求にあたり、最も手間やコストを抑えられる手段は任意での回収です。
ただ、一括や短い期間の分割であればさておき、長期にわたる場合には、任意で支払うとの約束があってもどこかで滞り、強制執行等が必要になる可能性もあります。
また、そもそも弁済を滞らせないように、もしもの場合の備えはしておきたいところです。
そのためには強制執行を可能とする債務名義を獲得しておきたいところですし、債務名義を獲得するには、相手が争っていないのであれば、判決よりも公正証書を作成するほうが簡便です。
「公正証書」の作成方法
公正証書の意義
損害賠償について合意が得られた場合には、公正証書を作成することで、万一支払いが滞った際に裁判を経ずに強制執行が可能になります。
公正証書は、債務者が支払いを怠った場合に、直ちに強制執行手続きに移行できる強力な書面となります。
公正証書の作成手続き
作成には公証役場での手続き必要であり、費用と必要書類も事前に確認しておくことが大切です。
具体的には、以下の手順で進めます。
- 債権者と債務者が合意した内容を文書化する。
- 公証人に内容を確認してもらい、公正証書として作成する。
- 作成された公正証書に執行認諾文言を付すことで、強制執行が可能な書面となる。
公正証書の作成には、手数料が発生しますが、将来的な法的手続の簡略化を考慮すれば、費用対効果は高いといえます。
従業員側としても支払いを滞れば強制執行されてしまうので、頑張って弁済を続けようという気になりますから、分割で支払いを受けるのであれば公正証書の作成は必須といえるでしょう。
4.刑事告訴という選択肢
刑事告訴は、犯罪に該当する行為を行った従業員に刑事責任を負わせる手段であり、社会的制裁を与える効果もあります。
刑事告訴を行うことで、再発防止や他の従業員への抑止力となることも期待されます。
刑事告訴を行うには、以下の手順が一般的です。
- 事実関係の確認・証拠収集を行う
- 告訴状の作成、添付する証拠資料の整理を行う
- 警察署または検察庁に告訴状を提出する
- 必要に応じて補充や説明等を行い、告訴を受理してもらう
- 捜査機関による捜査が開始される
- 必要に応じて、企業関係者が捜査機関の事情聴取を受ける
- 捜査結果に基づき、起訴または不起訴が決定される
- 起訴された場合、裁判で刑罰が科される
ただし、捜査や裁判の過程で社内混乱が生じたり、報道により不祥事が明るみに出るといったリスクもあるため、対応は慎重に検討する必要があります。また、刑事事件として立件されるためには、犯罪に該当する事実を証明しうる確実な証拠が求められる点にも留意が必要です。
5.再発防止等の観点も重要
従業員の不正等が発覚した場合、その対応が他の従業員に与える影響も大です。組織全体のモラル維持や企業価値の保護のためにも、再発防止策や対外的な対応を徹底することが重要です。
たとえば:
- 内部通報制度の整備
- 社内監査体制の強化
- 従業員教育の徹底
- 不正防止や懲戒を明記した就業規則の見直し
- プレスリリースやマスコミ対応等
不正を「起きたこと」として終わらせず、組織の健全性を見直す契機とすることが企業としての責任です。
6.弁護士への早期相談が鍵
従業員による不正行為等は企業にとって大きなリスクですが、適切な対応と再発防止策を講じることで、損害の拡大防止や回復を図るとともに、組織の健全性を保つ契機とすることもできます。
万が一不正等がうかがわれる場合には、まずは事実確認、証拠収集等に行った上、懲戒処分や解雇、損害賠償請求や刑事告訴等、適切な法的手段をとることが必要です。
被害の拡大を防ぎ、可能な限りの回復を図るためにも、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。

弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。







 LINEで
LINEで