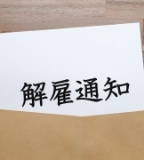逮捕されたくない

逮捕を回避するには?元検事の弁護士が逮捕される場合や回避のポイントについて解説
「犯罪をしてしまい、捜査されているかもしれない」「被害届や刑事告訴をすると言われた」「警察から呼出しを受けた」など、「もしかしたら逮捕されるかもしれない」といった不安を抱えている方は少なくありません。
ただ、世の中で発生している犯罪に当たりうる全てのトラブルが刑事事件として立件されるわけではありませんし、刑事事件として立件されれば必ず逮捕されるわけでもありません。
むしろ、刑事事件として立件まではされないトラブルや逮捕はされないままいわゆる「在宅事件」として捜査が続いていく事件が多数です。
逮捕の要件は法律上定められていますし、逮捕するとその後の時間的制約も生じるため、捜査機関としても逮捕するには一定のハードルがあります。事案の性質や逮捕の意義等を理解した上、迅速かつ適切に手を尽くすことにより、逮捕を回避できることもあります。
この記事では、逮捕とは何か、どのような場合に逮捕されるのか、そして逮捕を回避するため具体的に何ができるのかについて、元検事の弁護士の視点からわかりやすく解説します。
目次
そもそも逮捕とは?
逮捕の定義と種類
逮捕とは、刑事手続の中で、被疑者の身体の自由を一時的に奪う処分であり、
次の3つの種類があります。
現行犯逮捕:犯罪を現に行っている、または犯罪を行った直後の状況で行われる逮捕をいいます。
この場合は事件から間もなく逮捕されることになるのでその間になにか対応ができるわけではありませんが、勾留の阻止等で早期の釈放を目指していくことになります。
通常逮捕:裁判官の発付する逮捕状に基づき行われる逮捕をいいます。
逮捕の類型で最もスタンダードなものであり、捜査機関(多くは警察)が逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の要件があると判断した場合に逮捕状が発布されます。
緊急逮捕:重大な犯罪については、現行犯逮捕の要件まではない状況であっても、「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」場合には「緊急逮捕」をすることができます。なおこの場合、逮捕後に逮捕状を請求する必要があり、もし発布されなければ釈放しなければなりません。
逮捕されるとどうなるのか
逮捕されると身柄の拘束が始まり、警察署に連行されて取調べ等を受けることになります。
多くの場合、検察庁へ送致された上、勾留が請求され、裁判所が認めると最大で23日間身柄を拘束され続けることとなります。
さらに、検察官により起訴されるとその後も被告人としての勾留が継続し、保釈が認められるまで、あるいは判決等まで身柄を拘束され続ける可能性もあります。
逮捕されると、その後勾留され、長期間にわたり身柄を拘束される可能性があります。
その間、外部との連絡が制限され、職場や学校に逮捕されたことが知られてしまうなどのおそれもあり、社会生活に大きな影響が出てしまいかねません。
したがって、逮捕そのものを回避することが、極めて重要となります。また、逮捕のタイミングで警察から報道発表がなされ、それがマスコミによって報道されるおそれもあります。
報道発表するか否かやそのタイミング、実際に報道するか否か、報道するとして実名等まで明らかにするかなどは捜査機関やマスコミの判断ですが、逮捕されたということは一定程度重大な事件であるという評価になるでしょうし、残念ながら社会一般の認識としては「逮捕されたということは実際に悪いことをしたのだろう」といった印象を抱かれるおそれもあります。
逮捕されたと報道されればその後不起訴になったとしても事実上大きな不利益を受けることになりかねず、その観点からも逮捕自体回避することが重要となってきます。
逮捕されるのはどのような場合か
法律上の要件
逮捕の要件は、法律上定められています。
ここでは、最も一般的な逮捕の類型である通常逮捕の要件を説明します。
通常逮捕は、単に犯罪の疑いがあるだけでなく、逃亡のおそれや罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあると裁判官に判断された場合になされます(刑事訴訟法199条2項)。
なお、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる比較的軽微な犯罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合や正当な理由なく出頭の求めに応じない場合でなければ通常逮捕されることはありません(同条1項ただし書)。
実際に逮捕されるのはどのような場合か
逮捕の法律上の要件は上記のとおりですが、捜査機関は、これらの要件を満たす全ての事案で逮捕するわけではありません。
逮捕してしまえば、基本的にその後の限られた身柄拘束の期間内に捜査を終えなければなりませんし(例外的に釈放して在宅で捜査が続けられたり、処分保留で釈放されると同時に別の事件で再逮捕されるといった場合もあります)、都市圏では留置施設が慢性的に不足しているといった状況にもあり、警察としても全ての事件で逮捕等すると弊害が生じうるという状況にあるのです。
そこで、逮捕の要件が認められそうな事件の中でも、事案の重大性や逃亡、罪証隠滅のおそれの程度などを考慮の上、より逮捕等の必要性が高い事件について逮捕しているというのが実情です。
事案によっては、逮捕状を準備した上、捜索差押えや被疑者の取調べを行ってみて、その供述状況や証拠の収集状況によって実際に逮捕するかを判断するといった場合もあるかもしれません。
逮捕するか否かの判断は事案ごと、さらにはその時点での捜査機関の状況にもよるところですので千差万別です。
法定刑の重い事件や社会の耳目を集める事件かどうか、共犯者がいるかどうか、どの程度証拠が収集されているか(裏を返せば隠滅の対象となるような証拠がまだ残っているか)、被疑者の立場(家族や定職があるなどの事情は逃亡のおそれを低減させうる事情です)や供述状況等の諸般の事情が考慮されるものと思料されます。
逮捕されることを事前に知ることはできるのか
通常、逮捕されると事前に察知することは困難であり、逮捕は突然やってきます。
通常逮捕の場合、捜査機関が事前に逮捕状の発布を受けているので、いつ逮捕するかはいわば捜査官のさじ加減で決まる部分もあります(とはいえ、その後の手続の便宜上、週末や連休前は避ける、午前の早い時間に行われる場合が多いといった傾向はあります。)。
法律用語ではなく俗語に過ぎませんが、「おはよう逮捕」といって早朝に突然警察がやってきて逮捕されることもあります。
逮捕はそもそも逃亡や罪証隠滅を防止するという機能を有するものですし、捜査自体、なるべく被疑者には秘密裡に行われる性質のものです。
「いついつ逮捕しますよ」と分かってしまえば、それまでの間に逃亡や罪証隠滅をされるおそれもあるところ、実際に逮捕するその時まで察知されないようにするのが捜査機関として当然の対応ですし、事前に把握することは難しいでしょう。
ただ、刑事事件について豊富な知見を有し、捜査機関側の事情や考え方も分かる弁護士等であれば、具体的にいつなのか、必ず逮捕されるのかといったところまでは分からなくとも、事案の内容や証拠関係を踏まえて捜査機関として逮捕しようと考えそうな事案か否かある程度の見当をつけることもありえます。
そして逮捕の可能性があるという事案については、いつその日が来るかも分からない以上、なるべく迅速に逮捕の可能性を低減させるべく手を尽くすべきでしょう。
逮捕されないために弁護士ができるサポート
では、逮捕を回避するために具体的にどのようなことができるでしょうか。
上記のとおり、逮捕の要件として①逃亡のおそれ②罪証隠滅のおそれがあるところ、これらの要件がない、あるいはそれぞれの「おそれ」がないとまでは言えないまでも、逮捕する必要性に乏しいといえるだけの事情を揃えるとともに、そういった事情を適切に捜査機関に伝えることも必要です。
具体的なサポートとしては、下記のようなものが考えられます。
①示談交渉等
被害者がいる事件の場合、示談を締結することが逮捕を回避するために重要です。
示談を締結し、被害者が被害届を取り下げたり、被害者が刑事処分を望まない旨の示談書を作成したりすることができれば、もはや捜査機関としては身柄拘束してまで捜査をする必要性は乏しいですし、被疑者側としても逃亡や罪証隠滅の動機も激減することにもなり、逮捕の可能性を大きく低減することができます。
それだけでなく、前述のような示談が成立すれば、最終的に刑事処分が不起訴となり前科が付かなくなる可能性も非常に高くなります。
②身元引受人の準備等に関するサポート
身元引受人を準備し、逃亡や罪証隠滅をしないようしっかり監督する旨の誓約書を作成してもらい事前に警察に提出することで、逮捕の要件である逃亡や罪証隠滅のおそれが低いことを示し、逮捕の可能性を低減することができる場合があります。
とはいえ、身元引受人になってくれれば誰でも同じというわけではありませんし、刑事弁護に精通した弁護士がサポートすることにより、相談者様の親族等適切な方に身元引受人になってもらうよう交渉した上、捜査機関から見ても信用できるような内容の誓約書を作成することが重要です。
③自首のサポート
法律上、捜査機関に発覚する前に自首をすることで、刑が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。
自首の効果はそれに留まらず、自ら犯人として出頭した上、併せて事件の経緯等をまとめた上申書を作成して提出したり、事件の証拠になりうる証拠をまとめて提出することにより、逃亡や罪証隠滅の可能性が低いことをアピールし、逮捕の可能性をも低減させることができます。法律上の「自首」に該当するためには犯罪や犯人が捜査機関に判明していないことが必要ですが、仮にもう捜査機関としては把握していても、事実上有利な情状にはなりますし、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを端的に示す効果もあることは変わりありません。
自首に至るまでの警察との調整や上申書の作成、証拠として提出すべきものの整理等、刑事弁護に精通した弁護士がサポートできることが多々あります。

弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。







 LINEで
LINEで