
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
業務外の病気やケガ(私傷病)で休職している労働者の休職期間満了が近い場合、使用者は、労働者の今後の処遇を考えなければなりません。
使用者の判断で休職期間を延長するという選択もありますが、そうでない場合、復職させるか、労働契約を解消するかを決めなければなりません。
労働者が完全に傷病から回復していれば、復職に問題はありませんが、回復が不完全な場合には、復職を希望する労働者と使用者との間で、トラブルを生じる可能性があります。
この記事では、業務外の病気やケガを理由とする休職期間満了後の労働者の処遇に関する注意点を解説します。
なお、業務上の傷病については、療養期間中とその後の30日間は、原則として解雇が禁止されています(労基法19条)。私傷病とは別の検討が必要になりますのでこの記事では取り扱っていません。
目次
1.休職制度の種類
休職とは、一定の事由がある場合に、労働契約を維持しつつ、ある程度の期間にわたり、労働者の就労を免除又は禁止する措置です。
この休職制度は法律で定められたものではなく、休職制度を採用するか否かは使用者の自由です。休職制度を採用する場合、通常は、就業規則に休職となる事由、休職期間、休職中の賃金、休職後の処遇等を明記します。
どのような休職制度を採用するのかは使用者の任意ですが、実務上の例として、以下のようなものがあります。
- ①私傷病休職(業務外の傷病による欠勤が一定期間に及んだときに行われるもの)
- ②起訴休職(刑事事件に関して起訴された者を一定期間又は判決確定までの間休職とするもの)
- ③事故欠勤休職(傷病以外の自己都合による欠勤(事故欠勤)が一定期間に及んだときになされるもの)
以下では、休職制度の代表例として、①私傷病休職制度について説明します。
2.私傷病休職制度における休職期間満了
私傷病休職における休職期間の長さは、勤続年数や傷病の内容に応じて決められます。
休職期間中に治癒して就労が可能となれば休職は終了して復職となり、治癒しないまま期間満了となれば、自動的に退職(自然退職)又は解雇となります。
自然退職となるか解雇となるかは、使用者の就業規則の定めによります。使用者は、休職期間満了を自然退職事由とするか、普通解雇事由とするかを選択して制度設計することができるのです。
3. 私傷病休職における休職期間満了後の労働者の処遇
3-1. どの程度傷病が回復したら「治癒」と評価され復職させるべきか
私傷病休職の期間満了後に、労働者が復職を希望したにもかかわらず、使用者が自然退職扱いや解雇をすると、その処遇の有効性について、使用者と労働者との間で争いとなることがあります。
使用者は、労働者の傷病が「治癒」して、労働契約上の労務提供義務を果たせるだけの労働能力を回復したのであれば、復職させるべきですし、そうでないなら自然退職又は普通解雇となります。
そのため、どの程度の労働能力の回復があれば「治癒」したと言えるのかが問題となります。
この点、「治癒」とは、かつては、傷病となる前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復した状態を表すとする考え方が支配的でした。
つまり、傷病前と同水準で労働能力が回復しない限りは、労務提供義務を果たすことはできないと評価していたのです。
3-2. 職種や業務内容を特定しない労働契約の場合
しかし、労働者と使用者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結していた場合には、従前の業務ができなくなったからといって、必ずしも労務提供義務違反とは言えないはずです。他の業務であれば就労できる場合があるからです。
そこで、今日では、職種や業務内容が限定されていない労働者につき、私傷病休職の期間満了時に、従前の業務に復帰できる状態ではないが、より軽易な業務には就くことができ、労働者もこれを希望している場合、使用者は現実に配置可能な業務の有無を検討する義務があり、軽減業務に就かせる措置をとらずに自然退職扱いや解雇を行った場合には、退職の効果は生じない、又は解雇権濫用として解雇は無効となると考えられています。
最判平成10年4月9日・片山組事件・労働判例736号15頁
建設会社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきた労働者が、疾病のため右業務のうち現場作業に係る労務の提供ができなくなった場合であっても、労働契約上その職種や業務内容が右業務に限定されていたとはいえず、事務作業に係る労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたときには、同人の能力、経験、地位、右会社の規模、業種、右会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして同人が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討した上でなければ、同人が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできない。
3-3.職種や業務内容を特定した労働契約の場合
他方、職種や業務を限定した労働契約が締結されていた場合は、従前の職種・業務が遂行可能な程度に回復していなければ、契約上予定された労務提供義務を果たせず、退職の扱い又は解雇は認められるはずです。
しかし、直ちに従前の業務に復帰できないとしても、比較的短期間で復帰可能な場合には、短期間の復帰準備期間を提供したり、復帰訓練の措置をとったりすることが信義則上求められ、このような措置をとらずになされた退職扱いや解雇は認められないと考えられています。
3-4.医師が復職可能と判断している場合
復職可能な程度に「治癒」したと言えるかどうかは、医学的な判断ではなく、あくまでも法的な判断です。
労働者の復職を受け入れるかどうかを使用者が決める際に、まず使用者が「治癒」したか否かを判断するのであり、それが争いとなったときは、最終的に裁判所が判断することになります。
もちろん、法的判断と言っても、医師による医学的見地からの意見を前提としていることは言うまでもありませんから、これを全く無視した判断はあり得ません。
東京地裁判平成22年3月24日・J学園事件・労働判例1008号35頁
うつ病により休職と復職を繰り返す職員に対する職務遂行への支障を理由とした解雇が争われた事案です。 裁判所は、解雇の当否を検討するにあたって、使用者が、主治医から治療経過や回復可能性についての意見を聴取しなかったことは「現代のメンタルヘルス対策の在り方として、不備なものといわざるを得ない」等と指摘し、解雇は無効であると判断しました。
しかし、休職期間満了時の治癒とは、一定の労務提供が可能か否かという見地から判断される概念ですから、労務の専門家でなく、職場の業務内容に精通していない医師の判断には限界があります。
また、使用者が医師の診断や意見を聴取しなかったとしても、事情によっては、必ず解雇や退職が無効となるわけではありません。
東京地裁平成24年3月9日判決・ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件・労働判例1050号68頁
休職期間満了後、労働者である原告が休職命令に先立って設定された人事部長との面談を一方的に放棄する一方で、休職命令それ自体に対しては特に異議等を述べなかったばかりか、使用者である被告から復職意思の有無や自然退職の注意喚起があったにもかかわらず、その意思さえあれば容易なはずの復職願を提出せず、そのまま本件休職期間の満了を迎えたものであり、被告において、退職扱いに先立って専門医等からの意見聴取を行わなかったことをもって、客観的合理性や社会的相当性に欠けるものということはできず、退職の扱いは有効である。
医師の診断は、「治癒」したかどうかの判断において重要な資料とはなりますが、判断材料の一つにすぎないのです。
4.労働者が診断書の提出を拒否する場合
休職期間満了後に労働者が復職を希望する場合、治癒の事実を証明する責任は労働者の側にあります。
東京地判平成26年11月26日・アメックス事件・労働判例1112号47頁
業務外傷病により休職した労働者について、休職事由が消滅した(治癒した)というためには、原則として、休職期間満了時に、休職前の職務について労務の提供が十分にできる程度に回復することを要し、このことは、業務外傷病により休職した労働者が主張・立証すべきものと解される。
また、使用者が治癒の判断をするにあたって、労働者は診断書の提出等によって協力する義務があり、診断書を提出しない場合、解雇もやむを得ないとした裁判例もあります。
大阪地決平成15年4月16日・大建工業事件・労働判例849号35頁
使用者が数回にわたって診断書提出期限を延期したにもかかわらず、労働者は、特に理由を説明することなく診断書を提出せず、通院先の病院の医師ではない医師の証明書なる書面を提出したのみで、医師への意見聴取をも拒否し続けており、使用者が休職期間満了後も直ちに労働者を休職満了退職扱いとせずに、自宅待機の措置をとっていたとの事情や、労働者自身が、未だ体調がすぐれない旨述べていることを合わせ考慮すると、使用者が、労働者に対し、就業規則の「精神又は身体に障害があるか、又は虚弱、老衰、疾病のために勤務たえないと認められた者」との規定に基づいて行った解雇は、社会的相当性を欠くとはいえない。
なお、診断書の提出を拒否する場合、産業医等、使用者が指定する医師への受診を命ずることも考慮に値します。
このような受診義務が就業規則に予め定められている場合(最高裁昭和61年3月13日判決・電電公社帯広局事件・労働判例470号6頁)はもちろん、就業規則等の定めがない場合でも、労働者の受診義務を認める裁判例があります(東京高裁昭和61年11月13日判決・京セラ事件・労働判例487号66頁)。
もっとも、受診命令の適法性に関するトラブルを防止するため、就業規則に「会社は、必要があると認めた場合、従業員に対し、会社が指定する医師の受診を命じることができる。」等の定めを設けるべきです。
最高裁昭和61年3月13日判決・電電公社帯広局事件・労働判例470号6頁
労働者である原告は、当時頸肩腕症候群に罹患したことを理由に健康管理規程26条所定の指導区分の決定がされた要管理者であったのであるから、原告には、公社との間の労働契約上、健康回復に努める義務があるのみならず、右健康回復に関する健康管理従事者の指示に従う義務があり、したがって、公社が原告の右疾病の治癒回復のため、頸肩腕症候群に関する総合精密検診を受けるようにとの指示をした場合、原告としては、右検診について被上告人の右疾病の治癒回復という目的との関係で合理性ないし相当性が肯定し得るかぎり、労働契約上右の指示に従う義務を負っているものというべきである。
5. 私傷病休職期間満了後の解雇通知、退職通知に関する注意点
私傷病休職期間満了により解雇とする場合は、原則として解雇日(労働契約を終了させる日)の30日前までに解雇予告を行うことが必要であり、解雇予告をしない場合は解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法20条)。
就業規則で休職期間満了により自然退職となる旨定められている場合、解雇予告の義務はありませんが、トラブルを避ける意味で、労働者に対し、事前に自然退職となる旨の通知書を送付しておくことが無難でしょう。
6. 退職金の支給に関する注意点
私傷病休職期間満了により退職又は解雇となった場合、退職金の算定にあたって、休職期間を勤続年数に算入するか否かが重要です。
勤続年数への算入の要否は、退職金規程あるいは就業規則に定められていれば、それに従います。何も定められていない場合は、保守的に、休職期間を勤続年数に算入するのが適切です。
また、自己都合退職と会社都合退職で、退職金の算定に差異を設けている場合は、これに従います。
7.お気軽にご相談ください
私傷病休職期間満了後に労働者を復職させるか、それとも解雇・退職とするかは、判断に迷うケースが少なくなく、判断を誤ると労働者との間で紛争になりかねません。
上原総合法律事務所では、労働問題に詳しい弁護士が、企業からのご相談をおうけしています。お気軽にご相談ください。

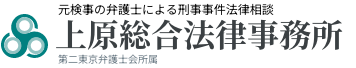


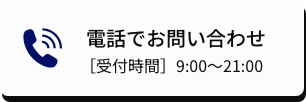


 LINEで
LINEで



